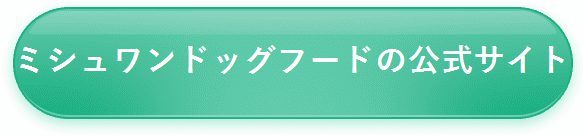ミシュワンの1日の給与量の目安を知りたい!体重別に早見表でチェック

愛犬の健康を守るためには、「何を食べるか」と同じくらい「どれくらい食べるか」も重要なポイントになります。
特に、フードの与えすぎや不足は体調に大きく影響を与えるため、正確な給与量の目安を把握することはとても大切です。
ミシュワンは全年齢・全犬種対応のドッグフードですが、それでも体重によって必要な栄養量は異なります。
日々の食事が愛犬の元気を支えるからこそ、適量をしっかり見極めたいですよね。
ここでは、ミシュワンの体重別の1日あたりの目安給与量を、わかりやすい早見表にまとめてご紹介します。
朝と夜の2回に分けた場合の1食分の目安量も記載しているので、日々のフード管理にぜひ活用してみてください。
ミシュワンの体重別の1日あたりの給与量について
ミシュワンの給与量は、愛犬の体重に応じて段階的に設定されています。
体重が増えるごとにカロリーの必要量も上がりますが、単純に比例するわけではないため、適量を知ることが大切です。
下記の早見表では、1kgから10kgまでの小型〜中型犬を中心に、1日に必要なミシュワンのグラム数をまとめました。
また、基本的に1日2回の食事を想定し、1回あたりの量も計算しています。
たとえば2kgのワンちゃんには約47g、5kgなら約94gが目安になりますが、あくまでも個体差や運動量によって多少の調整が必要です。
体重が同じでも消化力や体型によって変わることもあるため、便の状態や体重の増減を見ながら調整してあげるのが理想です。
| 愛犬の体重 | 1日の給与量の目安 | 1回あたり(2回に分けた場合) |
| 1kg | 約28g | 約14g |
| 2kg | 約47g | 約23.5g |
| 3kg | 約64g | 約32g |
| 4kg | 約79g | 約39.5g |
| 5kg | 約94g | 約47g |
| 6kg | 約108g | 約54g |
| 7kg | 約121g | 約60.5g |
| 8kg | 約134g | 約67g |
| 9kg | 約147g | 約73.5g |
| 10kg | 約159g | 約79.5g |
朝と夜でどう分ける?1日2回が基本だけど、ライフスタイルに合わせてOK
ミシュワンは栄養バランスが整っていて消化吸収にも優れているので、基本的には朝と夜の2回に分けて与えるのが理想的です。
1回あたりの量を調整しながら与えることで、胃腸に負担をかけにくく、1日を通して安定した栄養摂取が可能になります。
ただ、家庭のライフスタイルやワンちゃんの個性によっては柔軟な対応もOKです。
たとえば食が細い子やシニア犬、逆にエネルギーを多く使う子犬などは、1日3回に分けることで食べやすくなったり、消化がスムーズになることもあります。
大切なのは、愛犬のペースに合わせて「無理なく続けられるスタイル」を見つけてあげることです。
ミシュワンは消化が良く、栄養バランスも優れているから、基本は朝晩の2回食が理想
栄養価が高いミシュワンは、朝晩の2回でもしっかりと必要な栄養素をカバーできる設計になっています。
胃腸の負担も少なく、1回の食事量を適度に分けることで消化吸収の効率が良くなります。
特に成犬期や健康状態が安定しているワンちゃんには、2回食がちょうど良いリズムになりやすいです。
時間を決めて与えることで生活のリズムも整いやすくなり、落ち着いて食事を楽しめるようになります。
食が細い子や子犬、老犬は3回に分けてもOK
食べる量が少なかったり、1回にたくさん食べるのが苦手なワンちゃんには、朝昼晩の3回に分ける方法もおすすめです。
少量ずつ食べることで胃腸への負担も減り、栄養の吸収率が高まります。
特に子犬やシニア犬は消化力が弱くなっていたり、血糖値の変動を避けたい時期でもあるため、回数を増やして安定的に栄養を届けることが大切です。
忙しい飼い主さんは、自動給餌器や朝だけ手作り+夜にミシュワンなどのアレンジもOK
仕事や家事で日中に手が離せない方は、無理に完璧を目指さず自分のライフスタイルに合わせた工夫も大歓迎です。
たとえば朝は手作りフード、夜にミシュワンをしっかり与えるという使い分けや、自動給餌器を活用して時間通りに与えるなども選択肢に入ります。
大切なのは「栄養バランスを守ること」なので、ストレスなく継続できる方法で愛犬の健康管理をしていくのが一番です。
実はよくあるNG!体重じゃなく「なんとなく」で量を決めていませんか?
毎日繰り返すごはんの時間。
つい「このくらいかな?」と目分量であげてしまっていませんか?実はこれ、愛犬の健康にじわじわと影響するNG習慣なんです。
特に小型犬の場合、少しの量の差がカロリー過多や不足に直結してしまうこともあります。
「体重を基準にした量」を守らず、感覚で決めてしまうと、太りやすくなったり、逆に栄養が足りなかったりと、せっかくのプレミアムフードの効果が台無しになってしまうことも。
長く元気に過ごしてもらうためには、目安量をきちんと確認し、ライフステージや運動量に合わせてしっかり調整することが大切です。
ほんの少しの意識で、愛犬のコンディションは大きく変わってきますよ。
NG・「お皿いっぱいにすればOK」なんて感覚、要注意
お皿のサイズに合わせて「なんとなくたっぷり」にしてしまう…これ、意外とやっている方が多いんです。
でも実際には、それが愛犬の適正量を大幅にオーバーしていることも。
特に器が大きいと「まだ少ないかな?」と感じやすく、ついつい多く盛ってしまいがちです。
犬自身は満腹中枢が鈍く、出された分を全部食べてしまうこともあるので、食べるからといって「ちょうどいい」とは限りません。
お皿基準ではなく、まずは「その子の体重」と「フードのカロリー」で見直してみてください。
いつも元気に見えても、日々の積み重ねが将来の体調を左右します。
ちょっとした意識改革が、健康寿命を延ばす第一歩になりますよ。
NG・フードのカロリーは製品ごとに違うから、“前に使っていたフードと同じ量”では危険
実はドッグフードのカロリーは、ブランドごとにかなり差があります。
以前使っていたフードとミシュワンが同じグラム数でも、摂取できるカロリーが違うため、同じ量を与え続けてしまうとカロリーオーバーや栄養不足になるリスクがあるんです。
特にミシュワンのように高栄養設計のプレミアムフードは、少量でもしっかり栄養が摂れるようになっています。
「前と同じ量で大丈夫」と思わずに、まずはパッケージに書かれた給与量の目安を見直してみましょう。
そして、愛犬の体調や排便の様子、体型などを観察しながら微調整していくのが理想です。
これだけでフードの効果をより実感しやすくなりますし、健康を維持しやすくなります。
NG・正確に測るならキッチンスケール or 給餌カップを使ってね
「なんとなくスプーン1杯」「目で見た感じこれくらい」では、1日のうちに少しずつズレが出てしまいがちです。
毎回数グラムの違いがあると、月単位で見るとけっこうな差になりますよね。
そこでおすすめなのが、キッチンスケール(はかり)や専用の給餌カップの使用です。
これらを使えば1g単位で量を調整できるので、ブレがなくなり、安定してフードの効果を感じやすくなります。
ミシュワンは高品質で栄養価が高いからこそ、「きちんと適量」がとても重要です。
愛犬の健康管理をしっかりしたい方は、ぜひこのひと手間を習慣にしてみてくださいね。
慣れてしまえばほんの数秒の作業ですし、その分、愛犬の元気な姿が長く続いてくれます。
フードの量だけじゃダメ?おやつ・トッピングの“隠れカロリー”にも注意
毎日の食事管理で見落としがちなのが、フード以外から摂っている“隠れカロリー”の存在です。
愛犬にフードをきっちり測って与えていても、その合間にあげるおやつや、つい足してしまうトッピングの量が増えると、カロリーオーバーの原因になります。
特に、小型犬は体が小さい分、少しの余分なカロリーでも体重に大きく影響するんです。
おやつやトッピングはごほうびや栄養補助としてとても便利ですが、フードと合わせた1日の合計カロリーを意識してバランスを取ることが大切です。
「最近太ってきたかも」「食べる量は増えていないはず…」と思ったときこそ、おやつやトッピングを見直すサインかもしれません。
かわいいからとついあげすぎていないか、もう一度見直してみましょう。
おやつは1日の総カロリーの10%以内が理想
おやつは愛犬とのコミュニケーションやしつけのごほうびとして欠かせない存在ですが、実はこれがカロリー過多の原因になっていることが少なくありません。
一般的に、おやつは1日の総摂取カロリーの10%以内に抑えるのが理想とされています。
たとえば1日に300kcal必要な子なら、おやつは30kcal以内が目安ということですね。
つい“ちょっとだけ”のつもりで何度もあげてしまうと、気づけば一日の必要量を軽くオーバーしてしまうこともあります。
とくに高カロリーなジャーキーやチーズ系のおやつは、ほんの数グラムでも大きな差になります。
愛犬の体重管理が気になるなら、まずはおやつの頻度と量を見直すことから始めてみるのがおすすめです。
トッピングを多く使うなら、その分ミシュワンの量は減らして調整を
食いつきアップや栄養強化の目的で、フードにトッピングを加える方も多いですが、その分のカロリーをフードの量から差し引いていますか?鶏むね肉、さつまいも、野菜スープなどは一見ヘルシーに思えますが、重ねていくと意外にカロリーが積もります。
特にミシュワンのように栄養設計がしっかりされているプレミアムフードにトッピングを加える場合、必要以上の栄養やカロリーを摂ってしまうこともあるんです。
もしトッピングを使うなら、そのぶんミシュワンのグラム数を調整してあげるのが理想的です。
目安として、トッピングが全体の10〜20%を占めるなら、フード量も10〜20%ほど減らすように意識しましょう。
体重コントロールの近道は、こうした小さな配慮から始まります。
ミシュワンは少量でも栄養満点!だから“量が少ない=足りない”ではない
「なんだかフードの量が少ない気がする…」「うちの子、もっと食べたいのでは?」と心配になることってありますよね。
でもミシュワンは、一般的なフードとは設計がまったく違います。
実はこのプレミアムフード、少ない量でもしっかり栄養がとれるように、高たんぱく・高栄養で設計されているんです。
だから見た目の量が少なくても、それは“栄養不足”を意味するわけではありません。
むしろ過剰に与えすぎると、カロリーオーバーや体重増加につながることもあるため注意が必要です。
特に市販の安価なフードに比べて吸収率が高いため、体にちゃんと届く量が少なくても十分なんですね。
愛犬の満足そうな顔や体調の変化を見ながら、量より中身を信じてあげてください。
ミシュワンは高たんぱく・高消化性・栄養設計◎のプレミアムフード
ミシュワンの特長は、なんといっても「高品質な栄養設計」にあります。
国内産の鶏肉を中心に、良質なたんぱく質をしっかり含んでおり、消化吸収がよく体に負担をかけにくいのが魅力です。
さらにビタミン・ミネラル・オメガ脂肪酸・乳酸菌など、毎日の健康維持に欠かせない栄養素がバランスよく配合されています。
こうした成分が一粒一粒にぎゅっと詰まっているため、少量でもしっかり栄養を届けることができるんです。
「プレミアムフードは高いだけ?」と思われがちですが、実は必要量が少なくて済むからコスパも悪くないんです。
つまり、少ない量でも満足・安心のごはんが叶うのが、ミシュワンの強みなんです。
市販の安価なフードより吸収率が高いから、実は必要量が少なくて済む
市販のドッグフードの中には、かさ増しのために消化に負担がかかる穀物や添加物が多く含まれているものもあります。
そういったフードでは、見た目の量は多くても、実際に体に吸収される栄養は少ないこともあるんです。
そのため、飼い主としては「もっとあげないと足りないのでは?」と感じてしまいがちですが、ミシュワンのように消化吸収の良いフードなら、体に届く栄養の効率が違います。
つまり、量が少なくても“質”が高ければ、それで充分ということです。
特に高吸収な動物性たんぱく質が中心となっているため、少量でもしっかりエネルギーになり、便の量が減るなどのメリットも期待できます。
フード選びでは、ぜひ「見た目の量」ではなく「中身の質」で判断してみてくださいね。
給与量はどうやって計算する?ライフステージ別・運動量別の調整ポイント【ミシュワン給与量の計算方法】
愛犬にぴったりな給与量を把握することは、健康管理の第一歩です。
ドッグフードの袋に記載されている目安量はとても参考になりますが、それだけに頼ってしまうのは少し不安もありますよね。
犬は年齢や体重だけでなく、運動量や季節、性格によっても必要なカロリーが変化します。
特に、子犬と成犬、そしてシニア犬では消化能力や代謝のスピードがまったく異なるため、ライフステージごとに与える量を見直すことが大切です。
ミシュワンは全年齢対応のフードとして設計されていますが、それでも「その子の今」に合った量を与えることが、長く健康でいられるカギになります。
ここでは、年齢別の給与量目安や、調整するポイントについて詳しくご紹介していきます。
ライフステージ別に違う!年齢や成長段階で必要なカロリーは変わる
犬の体は成長段階ごとに必要とする栄養バランスやエネルギー量が異なります。
例えば、子犬は骨格や筋肉、臓器が急成長するため、エネルギー消費が多く、成犬よりも多くのカロリーが必要になります。
その一方で胃が小さいため、一度にたくさん食べるのは難しいため、食事を小分けにしてあげる工夫が必要です。
成犬になると成長は落ち着きますが、活動量の個体差が大きく、飼い主さんの生活スタイルによっても必要カロリーは変動します。
シニア犬になると代謝が低下し、運動量も減少するため、同じ量を与えていると肥満になってしまうことも。
年齢ごとの特性を理解して、給与量を柔軟に見直すことで、より健康的な体を保ちやすくなります。
| 年齢 | 特徴 | 給料量調整の目安 |
| 子犬(〜1歳) | 成長が早く、エネルギー消費が多い | 成犬の1.2〜1.5倍を目安に(※小分けが◎) |
| 成犬(1歳〜7歳) | 安定期。体格も落ち着く | ミシュワン推奨量が基本ベース |
| シニア犬(7歳〜) | 代謝が落ち、運動量も低下 | 基本量の80〜90%に抑えるのが◎ |
「成犬の量=すべての犬に適量」ではない!
ドッグフードのパッケージにある「成犬〇kgの場合はこのくらい」という記載、ついそれだけを信じてしまいがちですが、実際にはそれがすべての犬に当てはまるわけではありません。
同じ体重でも運動量が多い子、部屋の中でゆったり過ごす子、去勢・避妊手術をしている子など、条件が違えば必要なエネルギーも大きく変わってきます。
食べすぎれば肥満につながり、足りなければ栄養不足や元気のなさにつながることもあるため、「うちの子はどんな生活をしているか」をしっかり観察して調整することが大切です。
フードの量はあくまでスタート地点。
そこから日々の様子を見ながらベストなバランスを探していく姿勢が、健康寿命を延ばすことにもつながります。
年齢によって吸収・消化能力や活動量が変わるから、ライフステージごとの見直しが大切
犬の体は年齢によって大きく変化していきます。
若い頃は消化酵素も活発で、エネルギーの吸収もスムーズですが、年齢を重ねるとその機能は徐々に落ちていきます。
すると、今までと同じ量でも「吸収しきれない」「お腹がゆるくなる」「体重が増えやすい」といった問題が出てくることもあります。
また、活動量も年齢とともに減少するため、必要なカロリーも変わってくるのです。
特にシニア犬の場合は、過剰な摂取が内臓に負担をかけることもあるので、年齢に応じたフード量への見直しが重要です。
愛犬の様子を観察しながら、定期的にフードの見直しを行うことで、今の体に合ったベストな食生活を維持することができます。
活動量の違いでも調整を!室内犬とアクティブ犬では必要量が異なる
愛犬の体型や健康を維持するためには、「何グラム与えるか」だけでなく「どれくらい動いているか」も見逃せないポイントです。
たとえば、同じ体重のワンちゃんでも、毎日ソファでのんびり過ごす子と、毎朝ランニングしている子とでは、当然ながら必要なカロリー量は違ってきますよね。
ミシュワンの給与量はあくまで基準であり、そこから日々の活動量に応じて調整するのが理想です。
運動量が少ない子に基準どおり与えると太りやすくなりますし、逆に活発な子に少なめにしてしまうと、体重が落ちすぎたり、元気がなくなる原因にもなります。
愛犬の生活スタイルに合わせてフード量を見直すことは、じつは健康寿命をのばすためにも、とても大切なことなんです。
以下の表を参考に、無理のない範囲で調整してあげてください。
| 活動量 | 特徴 | 給与量調整の目安 |
| 低活動(室内犬) | 留守番が多い、散歩短め | 基本量の90〜95%でOK |
| 標準活動 | 毎日30〜60分の散歩あり | ミシュワン推奨量どおりでOK |
| 高活動(外遊び・スポーツ犬) | ランニング・運動大好きタイプ | 基本量の110〜120%で調整 |
「ちょっと太った?」「最近ごはん残すな…」というときは、活動量に見合ってない量になってるサインかも
毎日決まった量を与えているのに、「あれ?体型が変わってきた…」と感じたことはありませんか?それ、もしかすると今の給与量が愛犬の活動量と合っていないサインかもしれません。
たとえば、雨の日が続いて運動不足気味のときに、いつも通りの量をあげていると、少しずつ体重が増えてしまうことがあります。
逆に、よく動いているのにフードが足りていなければ、ごはんを残す・体が細くなるなどの変化が見られることも。
愛犬の体調は日々変化するものなので、毎月の体重チェックや便の様子を見ながら、「今の生活に合っているか?」を振り返ってみてください。
少しの見直しで、ぐっと健康的な毎日をサポートできるはずです。
避妊・去勢後は要注意!太りやすくなるから少し調整を
愛犬が避妊・去勢手術を受けた後、「なんだか少し太ってきたかも?」と感じる飼い主さんは少なくありません。
実はこれ、ホルモンバランスの変化によって代謝が落ち、脂肪がつきやすくなる体質になってしまうためなんです。
術後はエネルギーの消費が減り、今までと同じ食事量では太りやすくなってしまうため、少し給与量を見直す必要があります。
おすすめは、今までの基本量から5〜10%ほど減らすこと。
さらに、あまり運動をしない子や室内で静かに過ごすことが多い場合は、15%ほどの調整も検討してみてください。
もちろん、急激に減らすのではなく、愛犬の体調や体型の変化を見ながら、少しずつ減らしていくのが安心です。
日々の様子をよく観察しながら、術後の体重管理をしっかりしていきましょう。
ホルモンバランスの変化で代謝が落ち、脂肪がつきやすくなる
避妊・去勢を行うと体内のホルモンバランスが変化し、性ホルモンの働きが弱まることで基礎代謝が落ちてしまう傾向があります。
この結果、同じように運動していても脂肪が燃焼しにくくなり、体に蓄積しやすくなるのです。
特に小型犬の場合は体脂肪がつきやすいため、ちょっとした食べすぎでも体重が増えやすくなってしまいます。
見た目には「少し丸くなった?」程度でも、じわじわと肥満リスクが高まってしまうので要注意です。
毎日のごはんが健康に直結するからこそ、術後のフード管理は丁寧に行っていくことが大切です。
去勢・避妊後の愛犬には、基本量から5〜10%減らすのがおすすめ
フードの切り替えや新しい食生活を取り入れるときに大切なのは「少しずつ、無理なく調整すること」です。
ミシュワンは全年齢対応で栄養バランスに優れたフードなので、去勢・避妊後でも続けて与えることができますが、体に合わせた量の調整が必要になります。
基本量の5〜10%を目安にしながら、まずは1週間〜10日程度かけて少しずつ減らしてみましょう。
そのうえで、愛犬の便の状態、体重の変化、元気の度合いを観察し、必要に応じてさらに微調整を加えていくのが理想的です。
いきなり大幅に減らしてしまうとストレスや栄養不足になる可能性もあるため、あくまでもゆるやかな調整がおすすめです。
| 状況 | 調性目安 |
| 避妊・去勢済み | 給与量を5〜10%減 |
| 去勢+低活動 | さらに抑えて15%減も検討 |
| 痩せすぎの場合 | 維持 or 栄養補助の相談も◎ |
体型チェックで“適正量かどうか”を日々確認しよう
フードの量を調整するには、愛犬の体型を目で見て、触ってチェックすることが何よりも大切です。
体重だけで判断するのではなく、全体のシルエットやお腹周り、肋骨の触れやすさなどから「ボディコンディションスコア(BCS)」を確認する習慣をつけましょう。
たとえば、理想体型とされるBCS3では、肋骨は触れるけれども見えず、ウエストにくびれがある状態です。
逆に太り気味のBCS4~5になると、肋骨が触れづらく、体全体が丸く見える傾向があります。
痩せすぎの場合は、肋骨が目立って見えるほどです。
ミシュワンの給与量はパッケージに記載された目安を基本としながら、このようなBCSを目安に10〜20%の増減を調整していくことで、より愛犬に合った体型管理が可能になります。
| スコア | 見た目の特徴 | 給与量の目安調整 |
| BCS 3(理想) | 肋骨は触れるが見えない。ウエストくびれあり | 現状維持でOK |
| BCS 4〜5(太め) | 肋骨が触れにくい、くびれがない | 給与量を10〜15%減らす |
| BCS 2(痩せ気味) | 肋骨が浮き出て見える | 給与量を10〜20%増やす |
迷ったらどうする?まずは公式量を基準にスタートして様子を見るのが正解
フードの量に悩んだとき、最初から完璧を求めるのはなかなか難しいですよね。
そんなときは、まずミシュワン公式サイトに記載されている給与量を目安にスタートしてみましょう。
公式量は体重別に算出された一般的な基準で、多くのワンちゃんにとって無理のないスタートラインになります。
ただし、実際には個体差があるため、食べる量・動く量・年齢などを見ながら微調整が必要になります。
最初の2〜3週間は「うちの子に合っているかな?」と観察する期間として捉え、食べる様子や便の状態、体重の変化をチェックしてあげるのが良い方法です。
焦らず段階的に見直していくことで、愛犬にピッタリ合った“ちょうどいい量”がきっと見つかりますよ。
最初は公式サイトが出している給与量(体重ベース)に従う
ミシュワンでは、体重をもとにした給与量の目安が公式サイトにしっかり記載されています。
まずはその数値を基本にして、正確に計量して与えるところから始めるのが安心です。
「だいたいこのくらいかな?」という感覚ではなく、キッチンスケールなどを使って、1回の食事で何gなのかを明確にしておくことがポイントです。
特に最初は、基準量より多すぎず少なすぎず与えることで、愛犬の体調の変化を正しく観察しやすくなります。
もちろん、全ての犬に100%当てはまるわけではありませんが、最初の判断材料としてはとても役立ちます。
そこから実際の様子を見て、少しずつ調整していくことで、愛犬にぴったりの量を探っていけますよ。
2〜3週間ごとに「便の状態」「体重の変化」「食べ残しの有無」をチェック
給与量の見直しを行うタイミングとしておすすめなのが、2〜3週間ごとのチェックです。
変化はゆっくり起こるものなので、あまりに短期間で判断してしまうと正確な調整が難しくなってしまいます。
まずは便の状態を確認し、硬すぎず柔らかすぎない理想的な状態かをチェックしましょう。
また、体重も月に1〜2回は量っておくと、過不足が数値として分かりやすくなります。
さらに、フードを残しているかどうかも大切なポイントです。
毎回きちんと食べきっていれば量が合っている可能性が高く、逆に食べ残しが続くようであれば、何かしら調整が必要かもしれません。
こうした観察を習慣にすることで、愛犬の健康維持につながります。
問題があれば、少しずつ+5g/−5gで調整するのがベスト
もしも公式の給与量を守っているのに、体重が増えすぎたり、便がゆるくなったり、逆に痩せすぎたりしているようなら、少しずつ調整を加えてみましょう。
ただし、いきなり大幅に増減するのではなく、1日あたり5g単位で少しずつ変えていくのがポイントです。
変化が出るには時間がかかることもあるため、調整後は2〜3日〜1週間程度は様子を見ながら進めてください。
急に変えすぎるとお腹がびっくりしてしまう子もいるので、あくまで「ゆっくり、慎重に」が合言葉です。
理想的な体型や便の状態に近づいてきたら、その量を維持して様子を見るようにしましょう。
愛犬にとって心地よい食生活を作るために、丁寧な見直しを続けてあげることが大切です。
ミシュワンを子犬に与えても大丈夫?ミシュワン安全性と与え方の注意点
愛犬を迎えたばかりの頃、「どのフードを選べば安心なの?」「子犬でも大丈夫?」と迷ってしまう飼い主さんも多いのではないでしょうか。
特に子犬期は、成長に必要な栄養バランスや消化のしやすさ、安全性に対する不安がつきまといますよね。
そんなとき、無添加・国産・栄養設計にこだわったミシュワンが気になる方も多いと思います。
結論からいうと、ミシュワンは子犬にも与えることができるオールステージ対応のドッグフードです。
ただし、スタート時期や与え方には少し注意が必要です。
この記事では、公式の見解や対応時期、成長期にあたる子犬へのメリット、そして実際に与える際のポイントをやさしく詳しく解説していきます。
初めてのフード選びに悩む方にも、安心して読んでいただける内容です。
ミシュワンは子犬にも使える?公式の対応と推奨時期について
ミシュワンは公式にも「生後3ヶ月以降の子犬から使用OK」とされています。
これはちょうど離乳が完了し、ドライフードの消化が安定してくる時期にあたります。
ミシュワンはAAFCO(全米飼料検査官協会)の基準を満たした「オールステージ対応フード」なので、子犬はもちろん、成犬やシニア犬にもそのまま与えることができます。
つまり、ライフステージが変わるたびにフードを切り替える必要がなく、ずっと同じフードで育てられるのは飼い主にとっても手間が減って嬉しいポイントです。
ただし、月齢が若いほど消化力に差があるため、最初はふやかして少量ずつ与えるなど、やさしいスタートを心がけましょう。
焦らずに、愛犬のペースに合わせるのがいちばんです。
公式見解:生後3ヶ月(離乳完了)以降の子犬から使用OK
ミシュワンは、公式サイトや販売元の案内でも「生後3ヶ月から使用可能」と明言されています。
この時期は、ちょうど離乳食からドライフードへの切り替えが完了する時期でもあるので、固形フードを消化・吸収する力がついてくるタイミングです。
まだ消化器官が未熟な子犬に対して、ミシュワンのような自然素材中心・無添加の設計はとても相性が良く、安心して使えるのが特長です。
特に、添加物に敏感な子や胃腸が弱い傾向のある犬種でも試しやすいという声が多く寄せられています。
初めて与える際は、少量をぬるま湯でふやかして与える方法がおすすめで、体調や便の様子を見ながら徐々に慣らしていくとスムーズです。
AAFCO基準を満たしている「オールステージ対応」だから、成犬・老犬も同じフードでOK
ミシュワンは、AAFCO(アフコ)と呼ばれる国際的なペットフードの栄養基準を満たして設計されています。
これは「総合栄養食」として、全年齢・全犬種に適応できる証明でもあります。
そのため、子犬期からスタートしても、成犬・シニア犬になるまでずっとミシュワンを使い続けることができるのです。
切り替えのタイミングでお腹を壊したり、食いつきが悪くなったりする心配が減るのは、大きなメリットですよね。
愛犬のライフステージが変わっても同じフードで安心して続けられることは、実は飼い主さんの精神的な負担をぐっと減らしてくれるポイントでもあるんです。
成長期のエネルギーにも対応できる設計で安心
子犬期は、体も心もぐんぐん育つ大切な時期。
エネルギー消費が激しく、タンパク質や脂質、ビタミン・ミネラルなどをバランスよく摂取する必要があります。
ミシュワンはそうした成長期に必要な栄養素をしっかりと網羅しており、特に国内産の鶏肉をメインに使用した高タンパクなレシピが特長です。
これにより、筋肉の発達や骨の形成を助け、健康的な発育をサポートします。
また、サーモンオイルやビフィズス菌、オリゴ糖といった腸内環境を整える成分も配合されているので、まだ不安定な消化機能にもやさしく寄り添ってくれます。
元気いっぱいに育ってほしい子犬のために、安心して選べるフードだと感じています。
子犬への与え方|ふやかす?回数は?段階的な進め方を解説します
子犬の食事は成長に直結するため、与え方に慎重になる飼い主さんが多いです。
離乳期の生後2ヶ月まではまだ固形フードを与えるのは控え、離乳食で栄養を補います。
3〜4ヶ月頃からは、固形フードをお湯でふやかして柔らかくし、消化しやすい状態にしてあげるのがおすすめです。
この時期は消化器官がまだ未熟なので、食べやすさを優先してあげることが大切です。
5〜6ヶ月になると徐々にふやかす量を減らし、そのままの状態でも食べられるようにしていきます。
7ヶ月以降は成犬食へと移行し、基本的にはそのままの固さで大丈夫です。
また、1日の食事回数も月齢によって変わり、離乳期は4〜5回、成長期は3回、成犬期は2回に減らしていくことが理想的です。
| 月齢 | 状態 | フードの与え方 | 回数 |
| 生後〜2ヶ月 | 離乳期 | ✖使用不可(離乳食) | 4〜5回/日 |
| 3〜4ヶ月 | 離乳後 | お湯でふやかす(15分程度) | 3〜4回/日 |
| 5〜6ヶ月 | 成長期 | 半ふやかし or そのまま | 3回/日 |
| 7ヶ月以降 | 成犬食移行 | そのままでOK | 2回/日(朝夕) |
子犬にあげすぎ注意!成犬と同じ給与量にしない
子犬は見た目よりも体が小さく、消化器官もまだ未発達のため、一度に大量のフードを与えるのはおすすめできません。
特に成犬と同じ給与量で与えてしまうと、胃腸に負担がかかりやすく、下痢や嘔吐などのトラブルを引き起こすリスクが高まります。
子犬の健康を守るためには、少量をこまめに分けて与え、体調や排泄の状態をよく観察しながら徐々に量を増やしていくことが重要です。
体が成長するにつれて消化力も向上していくため、給与量も適宜調整していきましょう。
適正な量を守ることで、元気に成長できる体づくりにつながります。
子犬は体が小さいわりに消化力が未熟だから、1回の量は控えめが基本
子犬の消化器官はまだまだ未熟で、食べたものを効率よく消化吸収できる能力が十分とは言えません。
そのため、一度にたくさんのフードを与えると消化不良になりやすく、体調不良を招く可能性があります。
量を控えめにし、1日に複数回に分けて少しずつ与えることで、胃腸への負担を減らし、消化機能を徐々に育てていくことができます。
これにより、便の状態も安定しやすくなり、健康的に育つための土台が作られます。
成犬の給与量をそのまま当てはめると、胃腸トラブルや下痢の原因になる
成犬の給与量は体が大きく、消化機能が成熟していることを前提に計算されているため、子犬に同じ量を与えるのは適切ではありません。
子犬に過剰な量を与えると、消化不良や腹痛、下痢といった胃腸トラブルの原因になることが多く、場合によっては成長にも悪影響を及ぼすこともあります。
子犬の健康を守るためには、体重や月齢に応じた適切な給与量を守り、徐々に増やしながら成犬の量に近づけていくことが大切です。
焦らずに愛犬の様子を見ながら進めていきましょう。
よくあるNGとその対処法|「食べない」「お腹を壊した」時のチェックリスト
愛犬が急にドッグフードを食べなくなったり、お腹を壊してしまうと飼い主としてはとても心配ですよね。
ミシュワンに切り替えた直後に起こりやすいトラブルをあらかじめ知っておくことで、慌てずに対応できるようになります。
まず「食べない」という場合は、粒の大きさが合わなかったり、フードの香りに慣れていないことが原因かもしれません。
そんな時はお湯でふやかしたり、すりつぶして与えたり、少し香りづけをしてみると効果的です。
また「下痢や軟便」は、急な切り替えや食べすぎが原因になることが多いため、少量ずつ前のフードと混ぜながら徐々に慣らしていくのがポイントです。
さらに「吐く」場合は、空腹時間が長すぎることが考えられるため、1日に3〜4回に分けて食事を与えることをおすすめします。
| 問題点 | 原因 | 対策 |
| 食べない | 粒が大きい/香りになれない | ふやかす/すりつぶす/香り付け |
| 下痢・軟便 | 食べすぎ/急な切り替え | 少量から/前のフードと混ぜる |
| 吐いた | 空腹時間が長すぎた | 1日3〜4回に分けて与える |
成長に合わせた切り替えを!子犬→成犬で給与量も変わる
子犬から成犬へと成長する過程で、体の大きさや代謝量がどんどん変わっていきます。
そのため、給与するフードの量も適宜見直してあげることがとても重要です。
具体的には、1〜2週間ごとに体重の増加や便の状態を観察し、必要に応じて給与量を調整していくと良いでしょう。
生後7〜9ヶ月頃には、成犬用の給与量を目安にして問題ありませんが、あくまで体格や体調、便の様子を見ながら判断するのが基本です。
もし定期便を利用している場合は、配送量や配送間隔もライフステージに合わせて柔軟に変更できるので、無駄なく利用できておすすめです。
成長に合わせたフード管理が、健康で元気な毎日を支えるポイントになります。
子犬は体が大きくなるたびに必要量も増えるから、1〜2週間ごとに見直しをする
子犬期は体が日々大きくなっていくため、必要なエネルギー量も頻繁に変わります。
こまめな体重測定とともに、フードの給与量も1〜2週間ごとに見直してあげることで、過不足のない栄養補給が可能になります。
多すぎると肥満の原因に、少なすぎると成長不足につながるため、こまかな調整が欠かせません。
元気な様子や排便の状態も合わせてチェックしながら調整することが大切です。
7〜9ヶ月頃からは成犬と同じ給与量を目安にOK(体格と便の様子で判断)
子犬の成長が落ち着いてくる7〜9ヶ月頃からは、成犬用の給与量を基準にしても問題ありません。
ただし、体格や体調、便の状態は引き続き観察し、必要に応じて微調整してください。
体重が急激に増えたり、便の硬さが変わったときは、すぐに給与量を見直すことが大切です。
成犬期の健康維持につながる基本のリズムを作る時期なので、しっかり管理してあげたいですね。
定期便を使ってるなら、1回の配送量や間隔も調整してあげて
定期便でミシュワンを購入している場合、ライフステージや食べる量の変化に合わせて配送量や配送間隔を変更できるのが便利です。
成長に伴って給与量が変わっても、次回の配送分を調整すれば、フードの無駄を減らすことができます。
また、急に多量を頼んでしまうと保存が難しくなることもあるため、適切なペースで受け取ることが健康管理にもつながります。
配送スケジュールを見直すことで、愛犬の成長にあったフード管理をしやすくなります。
【ミシュワンの給与量は合っている?】合っていないサインとは|よくあるNG例と対策を解説
愛犬の健康を守るうえで、毎日与えるフードの給与量が適切かどうかは非常に重要です。
給与量が多すぎたり少なすぎたりすると、体調不良や体重の変化、消化の問題などさまざまなトラブルの原因になってしまいます。
しかし、実際には「量はこれで合っているのかな?」と悩む飼い主さんも多いのが現状です。
そこで今回は、ミシュワンの給与量が合っていない場合に起こりやすいサインや、よくある失敗例をわかりやすく解説します。
愛犬が元気に過ごせるよう、日々の様子をチェックしながら、給与量の見直しや対策に役立てていただければと思います。
給与量が合っていないとどうなる?まずは見逃せないサインをチェック
| 症状 | 内容 | 可能性のある原因 |
| 食べ残しが多い | 毎回少しずつ残す | 量が多すぎる/好みに合わない |
| 便がやわらかい・下痢ぎみ | 毎回ゆるい便が出る | 消化不良・一度に多すぎる |
| 便がコロコロ・硬すぎる | 水分不足 or 給与量が少なすぎる | 水分を小まめに与える |
| 体重が急に増えた・減った | 体型チェックが必要 | カロリー過多 or 栄養不足 |
| 食いつきが悪い | いつもダラダラ食べる | フードへの飽き・量の見直しが必要な可能性 |
給与量が合っていない場合には、上記のような症状が見られやすいです。
たとえば毎回少しずつフードを残してしまうのは、単純に与える量が多すぎることが原因かもしれません。
また便の状態がゆるい場合は消化不良の可能性があり、硬すぎる場合は水分不足や給与量が少ないことが考えられます。
さらに体重の急激な変化や食いつきの悪さも見逃せないサインです。
日々の様子をよく観察して、愛犬に合った量を見極めてあげることが健康維持のポイントです。
よくあるNG①:「体重だけ見て量を決めている」
犬の給与量を決めるとき、体重は確かに重要な指標の一つですが、それだけで決めてしまうのは危険です。
実は同じ体重でも、年齢や運動量、体質によって必要なカロリーは大きく異なります。
特に避妊や去勢をした犬や高齢犬は代謝が落ちやすく、同じ量を与えていると太りやすくなってしまう傾向があります。
そのため、単に体重だけを基準に給与量を決めるのではなく、愛犬のライフスタイルや健康状態、活動量も考慮しながら調整していくことが大切です。
体重が安定していても体調に変化があれば、給与量を見直す良いタイミングといえます。
体重が同じでも、年齢・活動量・体質によって必要なカロリーは変わる
同じ5キロの犬でも、若くて活発な犬と年を取っておとなしい犬では、必要なカロリーは違います。
運動量が多い犬はエネルギー消費も高いため、同じ体重でも給与量を多めにする必要があります。
また体質的に太りやすい犬や、逆に痩せやすい犬もいるため、個体差を考慮して調整することが重要です。
これは特に去勢・避妊後の犬やシニア犬で顕著で、代謝が低下しやすくなるため、給与量を減らす必要があることが多いです。
日常の体重管理と共に、愛犬の食欲や活力もチェックしながら適切な量を見極めましょう。
よくあるNG②:「ごほうび・おやつのカロリーを計算に入れていない」
日々のフードの量は適切でも、おやつのカロリーを計算に入れていないケースは意外に多いものです。
おやつは1日の総摂取カロリーに加算されるため、特に甘いおやつや人間の食べ物を与えている場合、知らず知らずのうちにカロリーオーバーになってしまうことがあります。
ミシュワンのような栄養バランスが整ったフードを与えている場合は、おやつは全体の10%以内に抑えるのが基本です。
おやつを多くあげすぎると肥満や消化不良、栄養の偏りを招くこともあるため、フードの量を調整しながらバランスよく与えることが大切です。
フードの量は合っていても、おやつで1日100kcalオーバーなど
人間が見落としがちなのは、おやつやごほうびのカロリー。
100kcalは小型犬にとってはかなりのカロリー量で、これが毎日積み重なると体重増加の原因になります。
フードの量を減らすことなくおやつだけを増やしてしまうと、肥満のリスクが高まるだけでなく、フードを食べなくなることも。
愛犬の健康管理にはトータルのカロリーコントロールが必要なので、おやつも含めて食事全体のバランスを考えることをおすすめします。
よくあるNG③:「食いつきが悪い=量が少ないと思い込んでいる」
「最近食いつきが悪い」と感じた時に、量が少ないからもっと増やさなきゃと思い込むのは注意が必要です。
実は、食べきれないほど量が多すぎることが原因で、犬が食欲を失っているケースも少なくありません。
特に子犬やシニア犬は、一気にたくさんの量を与えると胃腸に負担がかかりやすく、吐き戻しや偏食を引き起こすことがあります。
こうした場合は、給与量を見直して少量ずつ数回に分けて与えるなど工夫をしてみると良いでしょう。
無理に量を増やすのではなく、愛犬の食べるペースや体調に合わせた調整が食いつき改善の鍵となります。
特に子犬やシニア犬は、一気に多くを与えると胃腸に負担がかかるだけでなく、偏食や嘔吐につながることもある
子犬や高齢犬は胃腸がまだ弱かったり、消化機能が落ちていることが多いので、食事の量や回数の調整がより重要です。
1回に大量のフードを与えると消化不良や嘔吐の原因になりやすいため、少量を数回に分けることが推奨されます。
また、食事の際は落ち着いた環境を整えることも大切です。
食欲が落ちていると感じたら量だけでなく、与え方やフードの状態も見直してみるのがおすすめです。
ミシュワンの給与量は?に関するよくある質問【FAQまとめ】
ミシュワンドッグフードを検討している方からは、「実際どのくらいの量を与えればいいの?」という質問がとても多く寄せられています。
特に初めてプレミアムドッグフードに切り替える方にとっては、給与量が多すぎても少なすぎても心配になりますよね。
ミシュワンでは、体重や年齢、運動量に合わせて適切な給与量の目安が設定されています。
小型犬の場合、例えば体重3kg前後の子であれば、一日あたり約60g前後が目安とされていますが、年齢や体格差によって多少の調整が必要になることもあります。
また、1日分を朝晩に分けて与えることで、消化の負担を軽くしてあげることができます。
フードの袋には分かりやすい給与量の表も記載されているので、まずはそこを参考にしながら、愛犬の様子を見て少しずつ最適な量に合わせていくと安心です。
気になる点があれば、獣医さんに相談しながら進めるのもおすすめです。
ミシュワンの給与量の計算方法について教えてください
ミシュワンの給与量は、愛犬の体重や年齢、運動量に応じて計算することが基本です。
公式サイトやパッケージに記載されている推奨量を目安にしつつ、成長段階や体調、活動レベルによって微調整していきます。
たとえば、子犬は成犬の1.2〜1.5倍のカロリーが必要で、小分けにして与えることが望ましいです。
シニア犬は代謝が落ちているため、基本量の80〜90%程度に抑えるのがポイントです。
あくまでも目安なので、愛犬の体型や排便の状態を日々チェックしながら調整しましょう。
関連ページ:ミシュワンの給与量は?計算方法や与え方・子犬に与えるときの注意点
ミシュワンをふやかして与える方法について教えてください
ミシュワンをふやかして与えると、特に子犬やシニア犬、噛む力が弱い愛犬にとって食べやすくなります。
方法は簡単で、フードにぬるま湯(40〜50度程度)を加え、5〜10分ほど置いて柔らかくするだけです。
香りも立ち、食いつきが良くなることが多いです。
ただし、ふやかしたフードは傷みやすいので、作り置きは避け、与える直前に準備するのがおすすめです。
愛犬の様子を見ながら、水分量やふやかす時間を調整してあげてくださいね。
関連ページ:「ミシュワン ふやかし方」へ内部リンク
ミシュワンを子犬に与える方法について教えてください
子犬期は特に栄養とエネルギーのバランスが重要な時期です。
ミシュワンは全年齢対応のフードですが、子犬にはパッケージ記載の給与量を目安に、1日3〜4回に分けて少量ずつ与えるのがおすすめです。
初めての切り替えは、今までのフードと混ぜながら徐々に増やすことで、消化器官への負担を軽減できます。
また、噛む力が弱い子犬には、ふやかして与えると食べやすく安心です。
体重や便の状態を確認しながら、適宜調整してあげることが大切です。
関連ページ:「ミシュワン 子犬 与え方」へ内部リンク
愛犬がミシュワンを食べえないときの対処法について教えてください
愛犬がミシュワンを食べない場合は、まず無理強いをせずに原因を探ることが大切です。
新しいフードに慣れていない可能性があるため、今までのフードに少しずつ混ぜて切り替える「トッピング法」がおすすめです。
また、ぬるま湯でふやかして香りを立たせると食いつきがよくなることもあります。
おやつの与えすぎや食事時間が安定していない場合も原因になるので、生活習慣の見直しも検討してください。
長期間食べない場合は健康状態のチェックも必要です。
関連ページ:「ミシュワン 食べないとき」へ内部リンク
ミシュワンドッグフードは他のフードとはどのような点が違いますか?
ミシュワンドッグフードは、獣医師監修のもとで開発され、ヒューマングレードの国産鶏肉や無添加の自然由来原材料を使用している点が大きな特徴です。
多くの市販フードに含まれがちな人工添加物やグルテンを排除し、消化に優しい設計で腸内環境の改善もサポートしています。
また、サーモンオイルやアマニ油を配合し、抗炎症作用や毛艶の改善にも効果が期待できるのが魅力です。
健康と安全性にこだわったフードとして、多くの飼い主さんから信頼されています。
ミシュワンは子犬やシニア犬に与えても大丈夫ですか?
ミシュワンは全年齢対応のドッグフードとして設計されているので、子犬からシニア犬まで安心して与えることができます。
特に子犬にとって大切な栄養素や、年齢とともに衰えがちな消化機能や関節のサポート成分がバランスよく配合されているため、ライフステージごとの悩みにも寄り添ってくれます。
ただし、成長段階によって必要なカロリーや給与量は異なるため、体重や年齢に応じて調整することが大切です。
例えば、活発に動く子犬には少し多めに、小柄で運動量の少ないシニア犬には控えめにといった具合に、愛犬の生活スタイルに合わせてあげてください。
定期的に体調や体型をチェックしながら、愛犬に合った食事管理を心がけると安心です。
ミシュワンは犬種・体重によって給与量を変えますか?
はい、ミシュワンの給与量は犬種そのものというよりも、体重や年齢、活動量を基準に調整するのが基本です。
たとえば同じ3kgの犬でも、運動量が多く筋肉質な子と、落ち着いた性格であまり動かない子では、必要なカロリーが異なってきます。
そのため、まずはパッケージや公式サイトに記載されている体重別の目安量を参考にしつつ、実際の様子を見ながら少しずつ調整していくことが大切です。
また、小型犬や超小型犬には食べやすい小粒タイプであることもミシュワンの魅力のひとつなので、愛犬が食べやすく、消化しやすい環境を整えつつ、体調や便の状態をこまめにチェックしていくと、適正な量が見えてきますよ。
他のフードからミシュワンにフードを変更するときの切り替え方法について教えてください
フードを新しく切り替えるときは、愛犬の体に負担をかけないよう、時間をかけてゆっくりと移行するのが大切です。
急にまったく違うフードに切り替えてしまうと、消化不良や下痢、食欲不振を引き起こす可能性もあります。
理想的な切り替え期間は7〜10日ほど。
初日は旧フードの8割、新フード2割程度から始め、徐々に割合を変えていきながら様子を見ましょう。
3日目には5:5、7日目には新フードを8割というように、段階的に移行することで、愛犬の胃腸にも優しく対応できます。
もし途中で便がゆるくなったり食欲が落ちるようなら、一度割合を戻して、もう少しゆっくり進めても大丈夫です。
焦らず、愛犬のペースに合わせて切り替えてあげてくださいね。
好き嫌いが多いのですが、ミシュワンをちゃんと食べてくれるのか心配です
好き嫌いのあるワンちゃんの場合、新しいフードに対する反応が気になりますよね。
ミシュワンは国内産の鶏肉を主原料に使っていて、香りも自然で食欲をそそる風味があるため、偏食気味の子でも比較的食いつきが良いという声が多く寄せられています。
ただし、やはり個体差はあるので、最初は無理せず少量から試してみるのが安心です。
与えるときにぬるま湯でふやかしたり、手から与えたりすることで、興味を引くこともあります。
また、トッピングに頼らず食べてくれるようになるまでは、根気よく様子を見守ってあげることも大切です。
無理強いせず、フードを“ごほうび”として楽しんで食べてもらえるような工夫をすると、徐々に慣れてくれることが多いですよ。
ミシュワンを食べてくれないときの対処法はありますか?
もしミシュワンを最初に与えたときに、あまり食べてくれないようであれば、いくつか試してほしい対処法があります。
まずは、与える時間を決めてメリハリをつけること。
ダラダラ置きっぱなしにせず、15〜20分たっても食べない場合は一度片付けて、次の食事時間まで待つようにします。
これによって「ごはんは今しか食べられないんだ」と学習してくれる子も多いです。
また、ぬるま湯でふやかして香りを立たせる、手で少しあげて安心感を与えるなどの工夫も有効です。
それでも難しい場合は、徐々にミシュワンの割合を増やしていく“切り替えステップ”をゆっくり試してみましょう。
一時的に食べない日があっても、焦らず、愛犬のペースに合わせて続けてあげることが大切です。
ミシュワンに変更したらお腹を壊してしまいました。対処法について教えてください
新しいフードに切り替えたとき、一時的にお腹の調子が崩れることはめずらしくありません。
特に敏感な子の場合、食材の違いや栄養バランスの変化によって、軽い下痢や便のゆるみが起こることがあります。
そんなときは、すぐに切り替えを中止するのではなく、まず量を少し減らして様子を見てみましょう。
また、以前のフードと混ぜて与える割合を戻し、もう一度時間をかけて切り替える方法に戻るのもひとつです。
水分補給はしっかり行い、食欲がある場合は急激な変化を避けることが大切です。
もし数日経っても症状が続いたり、元気がなくなるようであれば、獣医さんに相談してくださいね。
焦らず、愛犬の体に合ったペースで進めることが何より大切です。
ミシュワンの保存方法や賞味期限について教えてください
ミシュワンは無添加のフードなので、開封後の保存には少し気を使ってあげると安心です。
高温多湿や直射日光を避け、密閉容器やチャック付き袋で空気に触れないように保存しましょう。
夏場や湿度が高い場所では、冷暗所での保存がベストです。
できれば1ヶ月〜1.5ヶ月以内で使い切れるサイズを選ぶと、鮮度も保ちやすくなります。
また、ミシュワンの賞味期限は未開封の場合で製造から約1年程度。
開封後は空気や湿気によって風味や酸化が進むため、なるべく早めに使い切ることをおすすめします。
日付を書いたメモなどをつけておくと、管理もしやすいですよ。
愛犬の健康を守るためにも、新鮮な状態で毎日安心して与えられるようにしていきましょう。
参照: よくある質問 (ミシュワン公式サイト)
ミシュワン小型犬用ドッグフードを比較|給与量はどのくらいが適正?
ミシュワンを与えたいと考えている飼い主さんにとって、「どれくらいの量が適正なのか?」というのは非常に大きなポイントではないでしょうか。
給与量は愛犬の健康や体重管理に直結するため、しっかりと確認しておきたいですよね。
ミシュワンでは、犬の体重ごとに目安となる給与量が明確に設定されており、例えば体重3kgの小型犬であれば1日あたり約60gが推奨されています。
ただし、これには年齢や日常の運動量なども関係してくるため、あくまでスタートの参考値と考えるのが良さそうです。
市販の他フードと比べると、ミシュワンは栄養価が高く設計されている分、必要以上に与えるとカロリーオーバーになりやすいという面もあります。
そのため、与えすぎには注意が必要です。
愛犬の体調やうんちの状態を見ながら少しずつ調整していくことで、適正な給与量が見えてくるはずです。
慣れてくれば、犬自身が食べたがる量と満足度にも変化が見られてくると思います。
| 商品名 | 料金 | グルテンフリー | 主成分 | ヒューマングレード | 添加物 |
| ミシュワン | 約2,000円 | 〇 | チキン、野菜 | ✖ | 〇 |
| モグワン | 約2,200円 | 〇 | チキン、サーモン | 〇 | 〇 |
| ファインペッツ | 約1,800円 | ✖ | ラム肉、チキン | 〇 | 〇 |
| カナガン | 約2,300円 | 〇 | チキン、さつまいも | 〇 | 〇 |
| オリジン | 約2,500円 | 〇 | 鶏肉、七面鳥 | 〇 | 〇 |
| このこのごはん | 約2,800円 | ✖ | 鶏肉、玄米 | ✖ | 〇 |
| ネルソンズ | 約2,000円 | 〇 | チキン、野菜 | 〇 | 〇 |
| シュプレモ | 約1,500円 | ✖ | 鶏肉、玄米 | ✖ | 〇 |
| うまか | 約2,600円 | ✖ | 九州産鶏肉、野菜 | ✖ | 〇 |
【まとめ】ミシュワンの給与量は?計算方法・正しい与え方と子犬に与える際の注意点
今回は、ミシュワンの給与量について計算方法や与え方、子犬に与える際の注意点についてご紹介しました。
ミシュワンは愛犬の健康を考える上で重要な要素であり、適切な量を与えることが大切です。
給与量は犬の体重や年齢、運動量などによって異なるため、計算方法を理解して適切な量を与えるように心がけましょう。
また、ミシュワンを子犬に与える際には、成犬とは異なる栄養バランスや与え方が必要です。
子犬の成長段階や体調に合わせて適切な量を与えることが重要です。
さらに、子犬に与える際には与え方や与えるタイミングにも注意が必要です。
子犬の成長や健康を考えて、適切な方法でミシュワンを与えるようにしましょう。
愛犬の健康を考える上で、ミシュワンの給与量や与え方について正しく理解することは非常に重要です。
適切な量を与えることで愛犬の健康を守り、健康的な生活を送らせることができます。
愛情を込めてミシュワンを与え、愛犬との絆を深める良い機会として大切にしていきましょう。