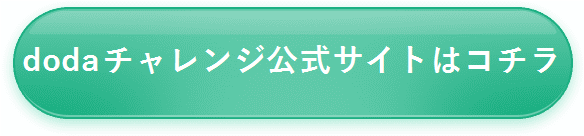dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や断られる人の特徴について解説します

dodaチャレンジを利用した方の中には、「登録したのに断られてしまった」という経験を耳にすることもあります。
断られる理由にはいくつかの背景があり、その多くは求人のマッチングに関するものです。
断られたからといって能力が否定されたわけではなく、あくまで条件や状況の不一致によるものが大半です。
ここでは代表的な理由を紹介し、どのように対応していけば良いのかを考えていきます。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジで断られる一番多い理由が、希望条件と紹介できる求人が一致しない場合です。
サービスとして求人が存在しなければ紹介はできないため、条件が厳しすぎると「紹介が難しい」という判断につながることがあります。
特に在宅勤務限定やフルフレックス、年収500万円以上など高い条件を設定している場合は該当する求人が限られてしまいます。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
条件を細かく設定しすぎると、その条件に合う求人は非常に少なくなります。
理想を追い求めることも大切ですが、ある程度の柔軟さを持つことで選択肢は広がります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
職種や業種を限定しすぎると、紹介される求人が極端に少なくなる可能性があります。
専門性の高い分野は求人数自体が少ないため、併用して他のサービスも検討すると安心です。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
希望する勤務地が地方に限られていると、都市部と比べて求人が少ないため紹介が難しくなることがあります。
この場合は在宅勤務や他地域での求人も視野に入れると可能性が広がります。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジは障がい者雇用に特化したサービスであるため、一定の条件を満たしていない場合にはサポート対象外と判断されることがあります。
たとえば、障がい者雇用枠の求人紹介を受けるには原則として障がい者手帳が必要です。
そのため、手帳を持っていない場合は求人を紹介してもらえないケースもあります。
また、長期間のブランクがあり職務経験がほとんどない場合や、現在の体調や状況が不安定で就労が難しいと判断される場合もあります。
その際は無理に就職活動を進めるのではなく、まずは就労移行支援を利用して準備を整えるよう案内されることもあります。
断られたからといって終わりではなく、次のステップへの助言がもらえる点も特徴です。
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠」での求人紹介は、原則手帳が必要)
手帳を持っていない場合は、障がい者雇用枠での紹介が難しくなります。
取得を検討している段階であれば相談できる場合もあるため、率直に状況を伝えることが大切です。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
ブランクが長いと求人紹介が難しくなることがありますが、訓練や実習を経て準備を整えることで再挑戦できる可能性があります。
状が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
就労が難しいと判断される場合は、就労移行支援を活用してスキルや体力を整えるよう促されることがあります。
段階を踏むことが結果的に安定した就労につながります。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
面談の場での印象や準備不足が、求人紹介を断られる原因になることもあります。
障がい内容や必要な配慮事項をきちんと説明できなかったり、自分がどんな仕事をしたいのかが曖昧なままだと、アドバイザーが適切な求人を提案できなくなってしまいます。
また、職務経歴がうまく伝わらないと、スキルや経験が把握されず、結果的に「紹介が難しい」と判断されることもあります。
面談に臨む際は、自分の状況や希望を整理してしっかり伝える準備をしておくことが大切です。
障がい内容や配慮事項が説明できない
配慮してほしいことを具体的に説明できないと、働き方のイメージが伝わらず、紹介が難しくなります。
事前に整理して言葉にしておくと安心です。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
仕事の希望が曖昧だと、アドバイザーも求人を探しにくくなります。
やりたいことや得意なことを事前に考えておくことが大切です。
職務経歴がうまく伝わらない
これまでの経験をうまく伝えられないと、アドバイザーが強みを把握できません。
具体的な実績やスキルを整理して伝えるようにしましょう。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
dodaチャレンジは全国対応のサービスですが、地域によって求人の数にはどうしても差があります。
特に北海道や東北、四国や九州などの地方では、都市部に比べて障がい者雇用の求人が少なくなる傾向があります。
そのため、希望条件を厳しく設定してしまうと紹介が難しくなることがあります。
また、完全在宅勤務のみを希望する場合も注意が必要です。
近年はリモートワークの求人も増えていますが、すべての職種で対応しているわけではなく、地方では特に数が限られます。
求人が少ない場合は、在宅と出社を組み合わせた勤務や、近隣都市まで通勤可能かどうかを検討するなど、条件を柔軟にすることで選択肢を広げられる可能性があります。
求人の量に地域差があることを理解し、現実的な視点で調整していくことが大切です。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
地方在住の場合は、都市部と比べて求人自体が少なく、紹介が難しくなることがあります。
通勤可能エリアを広げるなど工夫すると選択肢が増えることがあります。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
完全在宅勤務の求人は全国的に増えてきていますが、まだまだ数が少ないのが現状です。
希望を絞りすぎると紹介が難しくなるため、柔軟に働き方を検討することがポイントです。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
登録時の情報に不備や虚偽があると、信頼性の面から求人紹介を断られる可能性があります。
たとえば障がい者手帳をまだ取得していないのに「取得済み」と記載してしまうと、後の確認で不一致が発覚し、サポートが受けられなくなってしまうこともあります。
アドバイザーは正確な情報をもとに求人を探すため、事実と異なる内容を伝えるとマッチングに支障が出るだけでなく、企業側からの信頼を失う原因にもなります。
正直に状況を伝えれば、その時点でできる最適なサポートを受けられるので、無理に隠さず正確に登録することが大切です。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
手帳を持っていないのに「取得済み」と記載してしまうと、求人紹介は受けられなくなります。
申請中や取得予定であれば、その旨を正直に伝える方が安心してサポートを受けられます。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
体調や生活リズムが安定していないなど、働ける状況ではないのに無理に登録してしまうと、アドバイザーから「現段階でのサポートは難しい」と判断されることがあります。
焦る気持ちから登録してしまう方もいますが、就労が難しい状態のまま求人を紹介されても長続きしない可能性が高くなります。
その場合は、就労移行支援や医療機関のサポートを受けながら準備を整えることが推奨されます。
段階を踏んで就職に臨むことで、より安定して働き続けられる環境を見つけやすくなります。
職歴や経歴に偽りがある場合
職歴や経歴に虚偽があると、アドバイザーからの信頼を失い、求人紹介を受けられなくなる可能性があります。
採用選考の過程で事実と異なる内容が発覚すれば、企業からの信用も失ってしまいます。
経歴に自信が持てない場合でも、正直に伝えることが大切です。
アドバイザーはそのうえでサポートの方法を提案してくれるので、無理に取り繕わなくても安心して利用できます。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
dodaチャレンジで断られたと感じるケースの中には、実際には企業側からの不採用が理由となっている場合もあります。
これはアドバイザーが断っているのではなく、企業の選考基準や求めるスキルとの不一致によるものです。
たとえば、経験不足や専門知識の不足、他の応募者との比較で見送られることもあります。
つまり、dodaチャレンジに登録したから断られたのではなく、応募先企業の判断による結果ということです。
こうした場合は落ち込む必要はなく、フィードバックをもとに改善を重ねることで、次の選考につなげることができます。
不採用は企業の選考基準によるもの
不採用は企業が独自に定めている基準に基づくものです。
同じ人でも企業が変われば評価は異なるため、1社の結果にとらわれず、次に向けて準備を進めていくことが大切です。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか口コミや体験談を調査しました
dodaチャレンジを利用した方の中には、求人を紹介してもらえなかったり、サポート対象外と判断されてしまったという声もあります。
断られる理由はさまざまですが、その背景を知ることで、自分の就職活動をどのように準備すればよいかが見えてきます。
ここでは、実際に「断られた」と感じた方の体験談をまとめました。
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。
PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。
紹介できる求人がないと言われてしまいました
この方は障がい者手帳を持っていましたが、経験が軽作業に偏っており、PCスキルも最低限しかなかったとのことです。
そのため「紹介できる求人がない」と伝えられてしまいました。
求人紹介を受けるためには、ある程度のスキルや経験が求められることもあるため、スキルアップや資格取得を進めることが必要だと感じられる体験談です。
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
この方は就労に必要な安定性がまだ整っていないと判断され、まずは就労移行支援での訓練を勧められたそうです。
断られたこと自体はショックでも、支援を受けながら準備を進めることが、結果的に長く働ける環境を見つける近道になると伝わる体験談です。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。
dodaチャレンジに相談したものの、『ブランクが長く、就労経験が直近にないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう』と提案されました
この方は長期療養によるブランクが大きな理由で求人紹介が難しいと判断されました。
提案として「まずは体調の安定と職業訓練を優先しましょう」と言われたことで、就職を急ぐよりも段階を踏むことの大切さを実感したそうです。
すぐに働けなくても、準備を重ねることが未来につながるという気づきを与えてくれる体験談です。
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。
dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
この方は地方在住で、さらに在宅での専門職を希望していたため、求人自体がほとんどなかったとのことです。
結果的に紹介が受けられなかったのですが、地域や希望職種によっては求人が大きく制限されることがあるとわかります。
複数のサービスを併用したり、希望条件を柔軟にすることで可能性が広がることを感じさせる体験談です。
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。
dodaチャレンジに登録したら、『現時点では正社員求人の紹介は難しいです』と言われました
この方は正社員経験がなく、過去の経歴がアルバイトや短期派遣に限られていたことから、正社員求人の紹介が難しいと判断されました。
ただ、経歴が浅いからといって道が閉ざされるわけではありません。
契約社員やパートから経験を積んでいくことで、将来的に正社員を目指す道もあると理解できる体験談です。
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。
『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
この方は子育て中という事情から、在宅勤務や短時間勤務などの柔軟な働き方を希望していました。
しかし条件を重ねることで求人が極端に絞られてしまい、結果的に「ご紹介が難しい」と断られたとのことです。
家庭の事情に合わせた働き方を求めるのは大切ですが、条件をすべて同時に満たそうとすると求人の幅は狭くなってしまいます。
優先順位を整理し、何を一番大事にするのかを伝えることが重要だと感じさせる体験談です。
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。
dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
精神疾患の診断を受けているものの、障がい者手帳をまだ取得していなかったため求人紹介を断られたケースです。
dodaチャレンジは障がい者雇用に特化したサービスであるため、手帳の有無が利用の前提になることがあります。
この体験談からも、求人紹介を受けるには手帳取得が大きなカギとなることがわかります。
取得を検討している段階でも相談できる場合があるため、正直に伝えることが大切です。
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。
『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
この方はキャリアチェンジを希望していましたが、未経験で在宅エンジニア職を希望したため、求人紹介が難しいと断られたそうです。
エンジニア職はスキルや経験が重視される職種のため、未経験からの紹介は厳しいことがあります。
このケースからは、キャリアチェンジを考える場合に訓練や学習を積んでから相談することの大切さが伝わってきます。
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。
短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
通勤が難しいため短時間の在宅勤務を希望したケースですが、該当する求人がなく紹介が断られてしまいました。
求人は増えているものの、短時間かつ在宅という条件を満たす案件はまだ限られています。
この体験談からも、現実的に求人が少ない働き方を希望する場合は、複数のサービスを併用したり条件を少し広げる工夫が必要だとわかります。
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。
dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました
この方はハイキャリアを希望していましたが、障がい者雇用の枠では高収入や管理職の求人が非常に限られているため、紹介が難しいと伝えられました。
一般的に障がい者雇用では配慮が重視されるため、条件によっては求人の選択肢が極端に少なくなってしまいます。
高い条件を希望する場合でも、段階的にキャリアを積み重ねる視点を持つことが大切だと感じられる体験談です。
dodaチャレンジで断られたときの対処法について詳しく紹介します
dodaチャレンジで求人紹介を断られてしまうと、とても落ち込んでしまうものです。
しかし、断られるのは能力を否定されたわけではなく、あくまで「現状の条件では紹介が難しい」という判断であることがほとんどです。
ここでは、スキル不足やブランクなどでサポート対象外になってしまったときに役立つ具体的な対処法をご紹介します。
準備を進めることで、再挑戦のチャンスは必ず広がります。
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
スキルや職歴が不足している場合は、基礎から学び直すことで状況を改善できます。
ハローワークの職業訓練を利用すれば、無料または低額でWordやExcel、データ入力といったPCスキルを身につけることが可能です。
さらに就労移行支援を活用すれば、実践的なビジネススキルやビジネスマナー、さらにはメンタル面でのサポートも受けられます。
資格取得も効果的で、MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級を取得することで事務系の求人紹介の幅が広がりやすくなります。
小さなステップを積み重ねることで、アドバイザーからの評価も変わり、再度の紹介につながる可能性があります。
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
ハローワークの職業訓練は、費用の負担を抑えながらスキルを習得できるため、職歴が浅い方にとって大きな支えになります。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
就労移行支援を通じて、スキル面だけでなく心身の安定を整えられるのは大きな強みです。
訓練を通じて安定した就労を目指すことができます。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
資格は自分のスキルを客観的に証明できる手段です。
履歴書に書ける資格が増えることで、求人の選択肢が広がる効果があります。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養機関があるなど)の対処法について
ブランクが長い場合は、いきなり就職を目指すよりも、就労に向けた準備から始めることが大切です。
特に就労移行支援を利用することで、毎日通所して生活リズムを整え、安定した就労実績を作ることができます。
継続的に通所する習慣を身につければ、面接の際にも「安定して働ける」という実績として評価されやすくなります。
焦らず段階を踏むことで、自分に合った働き方に近づける可能性が高まります。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
長いブランクがある方でも、訓練を通じて徐々に働くリズムを取り戻すことができます。
準備期間を大切にすることが、就職成功への近道になります。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
ブランクがある方や働くことに不安がある方は、まず短時間勤務や在宅ワークから始めるのがおすすめです。
週に1〜2日でも継続して働けたという実績は、再びdodaチャレンジに登録する際の大きなアピール材料になります。
「この人は働き続けられる」という証明ができれば、求人紹介の幅が広がる可能性が高まります。
無理をせず自分のペースで始めることで、少しずつ自信を積み重ねていける点が魅力です。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
企業実習やトライアル雇用に参加するのも効果的です。
実際の職場で一定期間働くことで、スキルや体力だけでなく「就労継続が可能」という実績を積むことができます。
これらの経験は履歴書にも記載でき、次回の登録や面談で強いアピールポイントになります。
経験を積むこと自体が自分の自信にもつながるため、前向きな第一歩として取り組む価値があります。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
地方に住んでいると、どうしても都市部と比べて求人の数が少なくなり、紹介が難しいと感じることがあります。
そのようなときは、在宅勤務の求人やリモートワークに強い他のエージェントを併用するのも有効です。
また、地元に特化した支援センターやハローワークを活用することで、地域ならではの求人情報に出会えることもあります。
さらに、クラウドソーシングで小さな仕事を積み重ねることも「実績作り」につながります。
地方だからと諦めず、複数の手段を組み合わせて就職活動を進めるのが安心です。
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
在宅勤務に特化したサービスを併用することで、地方にいながら応募できる求人の幅を広げられます。
複数の窓口を利用するのが現実的な方法です。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
クラウドソーシングを活用すれば、自宅で取り組める仕事から実績を作ることができます。
経験を積むことで、自信とスキルの両方が身につきます。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地域の支援機関に相談すると、大手サイトには掲載されない求人や地域限定の情報を得られることがあります。
地元ならではの強みを活かすことができる点が魅力です。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
希望条件を細かく設定しすぎると、求人が極端に限られてしまい「紹介が難しい」と断られることがあります。
そのようなときは、まず条件に優先順位をつけることが大切です。
「これは絶対に譲れない」「これはできれば叶えたい」という基準を整理することで、アドバイザーも求人を探しやすくなります。
また、勤務時間や出社頻度、勤務地など譲歩できる条件を柔軟に見直すことで、新しい求人に出会える可能性が高まります。
さらに、段階的にキャリアアップを目指す戦略も効果的です。
最初は条件を緩めてスタートし、スキルや経験を積みながら理想の働き方へ近づけていくという流れです。
理想と現実をうまく調整することで、就職活動を前に進めることができます。
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
優先順位をつけることで、アドバイザーに伝える条件が整理され、求人紹介につながりやすくなります。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
譲歩できる条件を伝えることで、選択肢が広がり、マッチする求人を紹介してもらえる可能性が高まります。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
条件を一度緩めて働き始め、その後にスキルや経験を積むことで、希望の働き方を叶えやすくなります。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
dodaチャレンジでは、障がい者雇用枠での求人紹介を受けるために原則として障がい者手帳が必要となります。
そのため、手帳をまだ取得していない場合や、申請が難航している場合は紹介が難しいと断られてしまうことがあります。
そうしたときは、まず手帳の取得を検討することが重要です。
申請手続きには時間がかかることもあるため、早めに医師や自治体の窓口に相談することが安心につながります。
また、支援区分が合わない場合は、別の公的支援機関や地域の支援センターを併用するのも有効です。
手帳を取得することで求人の幅が大きく広がるため、将来の就職活動を見据えて準備を進めておくことが大切です。
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
障がい者手帳を持っていない場合は、まず主治医や自治体の窓口に申請について相談することが大切です。
精神障がいや発達障がいの場合でも、一定の条件を満たしていれば手帳を取得できるケースがあります。
手帳を持つことで障がい者雇用枠での求人に応募できるようになり、dodaチャレンジでのサポートも受けやすくなります。
取得までに時間がかかる場合もありますが、早めに準備を始めることで安心して次のステップへ進めるようになります。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳を持っていない段階では、就労移行支援やハローワークで「手帳がなくても応募できる求人」を探す方法もあります。
一般枠での就職活動を進めながら、就労移行支援で実績を積むのも有効です。
その後、手帳を取得してから改めてdodaチャレンジに登録し直すことで、より幅広い求人紹介を受けられるようになります。
段階的に進めることで、無理なく就労に近づくことができます。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
体調が安定していない場合や治療を優先したほうが良いときは、焦って登録するのではなく医師と相談しながら生活リズムや健康を整えることが第一です。
体調が安定すれば働ける幅も広がり、就労への準備がしやすくなります。
手帳を取得してから改めて登録することで、より安心してサポートを受けられるようになります。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
もしdodaチャレンジで断られてしまったとしても、就職活動の道が閉ざされるわけではありません。
他にも障がい者雇用に特化したサービスは存在しており、「リタリコ仕事ナビ」や「アットジーピー」、さらには地域ごとの障がい者就労支援センターなどを活用することで、新しい求人に出会えることがあります。
また、ハローワークでも障がい者専用の相談窓口があり、地域密着型の情報を得ることができます。
複数のサービスを並行して利用することで、自分に合った求人が見つかる可能性が高まります。
ひとつのサービスにこだわらず、選択肢を広げて取り組む姿勢が安心につながります。
dodaチャレンジで断られた!?精神障害や発達障害だと紹介は難しいのかについて解説します
dodaチャレンジを利用する中で「精神障害や発達障害だと求人を紹介してもらえないのでは」と不安に感じる方もいます。
しかし、断られる理由は障害そのものではなく、就労経験や体調の安定度、希望条件とのマッチングにあることが多いです。
精神障害や発達障害を持つ方でも、サポート体制を整えて準備を進めれば求人紹介を受けられるケースは少なくありません。
むしろ、障がいの特性に合わせて働き方を工夫しやすい職場も増えており、自分に合った働き方を見つけるために、まずは状況を正直にアドバイザーへ伝えることが大切です。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障害を持つ方の場合は、比較的就職がしやすい傾向があります。
理由のひとつに、障害の内容が外見的にわかりやすいことが挙げられます。
そのため企業側も合理的配慮をしやすく、安心して採用に踏み切れるケースが多いのです。
たとえばバリアフリー化や業務制限など、具体的にどのような配慮をすればよいかが明確になりやすいため、採用する側も負担を感じにくくなります。
また、障害の等級が低い場合は就業可能な範囲が広がるため、企業としても採用しやすいと考える傾向があります。
身体障がいのある方は、自分の状況をしっかり伝えることで、安定した職場につながる可能性が高まります。
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
等級が低ければ業務に制限が少ないため、幅広い職種での就職が可能になります。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
障害が明確にわかることで、企業も必要な配慮を事前に検討しやすく、採用の決断をしやすいといわれています。
企業側が合理的配慮が明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
バリアフリー化や業務分担など、具体的な配慮が明確に設定できるため、企業にとっても安心感があり採用が進みやすいのが特徴です。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
上肢や下肢に障がいがある場合は、どうしても通勤や作業内容に制約が生まれるため、求人の選択肢が限られてしまうことがあります。
たとえば立ち仕事や長時間の移動を伴う仕事は難しくなりますが、事務や在宅での仕事など、身体への負担が少ない分野では比較的求人が多く見つかります。
自分の状況を具体的に伝えることで、働きやすい環境を整えてもらえる可能性も高まります。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
身体障がいがあっても、コミュニケーションに支障がなければ一般職種に採用されるケースは多いです。
面接や職場でのやり取りがスムーズにできることは企業にとって安心材料となり、採用につながりやすくなります。
障がいの有無に関わらず、円滑なコミュニケーション能力は大きな強みとなります。
PC業務・事務職は特に求人が多い
身体障がいを持つ方の中でも、PC業務や事務系の仕事は特に求人が多い分野です。
バリアフリー化が進んでいるオフィスも増えているため、働く環境が整えやすいのが特徴です。
PCスキルを磨くことで、より多くの求人に挑戦できるようになります。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
精神障害者保健福祉手帳を持つ方の場合、就職活動では症状の安定性や継続勤務のしやすさが特に重視されます。
企業にとっては採用後の安定した勤務が何よりも大切なため、体調が整っているか、長く働ける環境を整えられているかを見られる傾向があります。
また、精神障がいは外から見えにくいため、企業が「採用後にどう対応すれば良いのか」と不安を持ちやすいのが現実です。
そのため、面接では必要な配慮事項を具体的に伝えることがとても大切です。
働きやすい環境を企業と一緒に作っていく姿勢を示すことで、安心して採用してもらえる可能性が高まります。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
体調が安定していることを示すことで、安心して採用につながる可能性が高くなります。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障がいは外見からわかりにくいため、企業がどう対応すれば良いのか迷うことが多く、不安を持たれる傾向があります。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
面接時に具体的に必要な配慮を伝えることで、企業も安心して準備ができ、働きやすい環境につながります。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
療育手帳を持つ方の就職事情は、手帳の区分によって大きく異なります。
A判定(重度)の場合は一般企業での就労が難しいことが多く、就労継続支援B型といった福祉的就労が中心になります。
無理に一般就労を目指すよりも、体調や生活リズムを安定させながら、福祉的な環境で働く方が安心して長く続けられることが多いです。
一方で、B判定(中軽度)の場合は一般企業での就労が視野に入りやすく、事務や軽作業、サービス業など幅広い分野での採用事例もあります。
知的障害のある方は、自分の特性に応じて実習やトライアル雇用を活用すると、企業に「働ける証明」を見せることができ、自信を持って就職に挑戦できます。
区分を正しく理解し、自分に合った働き方を探すことが、安定した雇用につながる大切なステップです。
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳は知的障害の程度を示す大切な指標であり、区分がA判定かB判定かによって選べる就労の幅が大きく異なります。
A判定の場合は支援を手厚く必要とするケースが多く、一般就労よりも就労継続支援などの福祉的な場が中心となります。
一方でB判定の場合は中軽度とされるため、一般就労も現実的な選択肢として考えられることが多いです。
区分は単なる数字や記号ではなく、その人に合った就労環境を見つけるための重要な基準となります。
自分の区分を正しく理解し、どのような支援が受けられるのかを整理することで、より適した働き方を選べるようになります。
区分の違いを知ることが、安心して就職活動を進めるための第一歩です。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定は重度の知的障害とされる区分であり、一般企業での就労は難しいケースが多いのが現実です。
そのため、福祉的な就労支援である就労継続支援B型が中心となります。
B型事業所では、体調や特性に合わせた作業を無理のない範囲で行えるため、安心して取り組むことができます。
また、福祉的就労は収入面では一般就労と比べると低めですが、生活リズムを整えたり社会参加の場としての役割を持つため、日々の安心感につながります。
A判定の方は無理に一般就労を目指すよりも、支援を受けながら継続できる環境を選ぶことが、長期的に見て安定した暮らしを支える大切なポイントとなります。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定は中軽度の知的障害とされる区分であり、一般就労の可能性が広がりやすい特徴があります。
たとえば、事務や軽作業、販売やサービス業など、多くの職種で採用のチャンスがあります。
もちろん、就労する際には本人の特性に応じた配慮が必要ですが、職場実習やトライアル雇用を通して働ける力を見せることで、企業も安心して採用に踏み切ることができます。
さらに、就労移行支援を利用すれば、面接練習や職業訓練を受けながら就職に向けて準備ができます。
B判定を持つ方は、自分の得意分野を見極めることで就職活動がスムーズになり、安定した職場での長期的な就労につながりやすくなります。
障害の種類と就職難易度について
障害の種類によって、就職活動の難易度には差があるのが現実です。
身体障害の場合は配慮事項が比較的明確で、バリアフリー化や業務制限といった対応がしやすく、企業にとっても採用のハードルが低いといわれています。
一方、精神障害や発達障害は外見から分かりにくいため、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすい傾向があり、面接時に配慮事項をしっかり説明することが不可欠です。
知的障害は区分によって就労可能性が変わり、支援機関を通した実習やトライアル雇用が特に重要になります。
どの障害であっても共通して大切なのは、体調を安定させ、必要な配慮を具体的に伝える準備を整えることです。
企業が安心して受け入れられるよう情報を共有することが、就職の成功につながります。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
就職活動を進めるうえで、障害者雇用枠と一般雇用枠の違いを理解することはとても大切です。
障害者雇用枠は、障がいを持つ人が安心して働けるよう法律に基づいて設けられた枠であり、企業が法定雇用率に従って積極的に採用を行います。
そのため、採用時には障害内容や配慮事項をオープンに伝えたうえで働くことが前提となります。
一方、一般雇用枠は障がいの有無に関係なく採用が行われるため、配慮を求めにくいこともあります。
どちらが正しい選択かは一人ひとりの状況によって異なりますが、自分に必要な配慮や働きやすさを考え、どちらの枠が適しているかを判断することが重要です。
特に安定した働き方を望む方にとっては、障害者雇用枠を利用するメリットが大きいといえます。
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠は法律に基づいて企業が設けているものであり、障がいを持つ人が安心して働けるように配慮されています。
採用段階から障害内容をオープンにするため、面接でも配慮事項を伝えやすい点が特徴です。
これは、一般雇用枠と大きく異なる部分です。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
企業は障害者雇用促進法に基づき、一定割合以上の障がい者を雇用する義務があります。
2024年4月からは法定雇用率が2.5%以上に引き上げられ、より多くの企業が採用に力を入れることになります。
この枠を利用することで、求職者は配慮を受けながら安定して働ける環境を見つけやすくなります。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
障害者雇用枠では、採用時に障害をオープンにし、どのような配慮が必要なのかを明確に伝えたうえで雇用されます。
そのため、入社後に「配慮が得られない」というトラブルが起こりにくく、安心して働き続けられるメリットがあります。
自分の状況を正直に伝えることで、企業も安心して採用できる環境が整うのです。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠は、障害の有無に関わらず全ての応募者が同じ条件で選考を受ける採用枠です。
そのため、選考では学歴や職歴、スキルや経験といった一般的な基準が重視されます。
障害がある場合でも特別な配慮を前提とせずに扱われるため、自分の能力をしっかりアピールできれば採用の可能性は十分にあります。
一方で、配慮を求めにくい環境であることもあり、働き方に制約が必要な場合にはミスマッチが起こりやすい面もあります。
自分の体調や特性に合わせて本当に一般枠で挑戦すべきかを見極めることが大切です。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
一般雇用枠では、障害を開示するかどうかは本人の判断に任されています。
オープン就労として障害を伝える場合は、一定の理解や配慮が期待できる一方で、伝えない「クローズ就労」を選ぶと、障害が考慮されずに働くことになります。
それぞれにメリットとデメリットがあり、オープンにするかどうかは職場環境や自身の働きやすさを考えて選ぶことが大切です。
特に継続的に働くためには、必要な配慮を受けられる環境かどうかを慎重に判断する必要があります。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠で働く場合は、特別な配慮や措置がないのが基本です。
企業側は他の社員と同じ条件で業務を求めるため、障害の影響がある場合には無理をしてしまうことも考えられます。
そのため、配慮が必要な人にとっては働きにくさを感じる場面も少なくありません。
ただし、本人の努力やスキル次第では活躍できる職場もあり、キャリアを積むことで将来的な選択肢を広げる可能性もあります。
自分に合う働き方を選ぶためには、配慮がなくても働けるかどうかを冷静に見極めることが欠かせません。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障害者雇用は年代によって状況が異なるといわれています。
実際、厚生労働省が公表している障害者雇用状況報告(2023年版)を見ると、若年層は採用に積極的な傾向があり、特に20代や30代前半では就職活動が比較的スムーズに進むことが多いです。
これはポテンシャルを重視する企業が多いためです。
一方で40代以降になると、即戦力や過去のキャリアが重視される傾向が強くなり、採用が難しくなる場合もあります。
ただし、経験やスキルを積んでいる人であれば強みとして評価されやすいこともあります。
年代による難しさはありますが、必ずしも年齢だけが不利に働くわけではなく、どの年代でも自分の強みを活かせる仕事を探すことが大切です。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
障害者雇用状況報告(2023年版)によると、法定雇用率の引き上げに伴い全体的な雇用者数は増加しています。
特に20代や30代の若年層は雇用が伸びており、企業も積極的に採用しているのが現状です。
40代以降ではやや難しさが見られるものの、専門スキルや豊富な経験がある場合は強みとして評価されやすい傾向があります。
つまり、年代ごとに異なる特徴を理解したうえで、自分の状況に合った戦略を立てることが就職成功への鍵となります。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。
未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。
経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
20代から30代前半の若年層は、障害者雇用の中でも特に採用が進みやすい年代といわれています。
企業がポテンシャルを重視する傾向があるため、スキルや職歴が浅くても「これから育成できる人材」として積極的に採用されるケースが多いのです。
また、求人数自体も比較的多く、未経験から挑戦できる事務職やサポート業務などの求人も豊富です。
この年代は、働き方の幅を広げやすいチャンスがあるため、まずは基礎的な経験を積み、長期的にキャリアを形成していく意識が大切です。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代を過ぎると、企業は即戦力としてのスキルや経験を重視する傾向が強くなります。
そのため、若年層のようにポテンシャル採用を期待するのは難しくなり、職歴や資格が不足していると求人の選択肢が狭まってしまいます。
ただし、実務経験や専門的なスキルを持っている人にとっては、むしろ高い評価を受けることもあります。
40代以降での就職活動は、自分の経験をどのようにアピールするかが重要となり、応募先に合わせて経歴やスキルを整理して伝える工夫が必要です。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代以上になると、体力や継続的な勤務への懸念から、求人が限られる傾向が強まります。
多くの場合、短時間勤務や特定の業務に限定された求人が中心となり、長期的なキャリアアップを前提とした採用は難しくなるのが現実です。
ただし、経験を活かした業務や専門分野での仕事であれば活躍の場を見つけることは可能です。
年齢に応じて無理のない働き方を選び、自分の強みを活かせる環境を探すことが大切になります。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
就活エージェントを利用する際に気になるのが年齢制限です。
公式には年齢制限は設けられていないため、幅広い年代の人が登録することができます。
しかし、実際には求人の多くが20代から50代前半をターゲットにしているため、それ以上の年代になると紹介される求人が少なくなることがあります。
これは企業が求める働き方やキャリア形成の長さを考慮しているためです。
年齢が高い場合は、経験やスキルを強調してアピールすることが特に重要になります。
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
dodaチャレンジをはじめとする障害者雇用のエージェントには明確な年齢制限はありませんが、現実的には50代前半までがメインの対象層とされています。
そのため、年齢が上がるにつれて求人が少なくなるのは自然な傾向です。
50代以降で利用する場合は、柔軟な条件を持ちながら経験を活かせる分野を探すことが鍵になります。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
年齢が高く求人が限られると感じる場合は、ハローワークの障がい者窓口や地域の障がい者職業センターを併用するのがおすすめです。
これらは地域密着型で求人情報を持っているため、大手エージェントでは紹介されにくい仕事に出会える可能性があります。
複数のサービスを使い分けることで、年齢に関係なく自分に合った職場を見つけられる確率が高まります。
dodaチャレンジで断られたときの対処法についてよくある質問
dodaチャレンジは障がい者雇用に特化した就職支援サービスですが、利用者の中には「断られた」「連絡がなかった」と不安を感じる人も少なくありません。
こうした場面に出会ったときに、どうすれば良いのかを理解しておくことが安心につながります。
口コミや評判を確認して実際の雰囲気を知ったり、断られた場合の対処法を理解することで次の行動が取りやすくなります。
また、面談後に連絡が来ない理由や面談の流れを事前に知っておけば、準備不足を防ぎやすくなります。
ここではよくある質問をまとめ、利用前に知っておきたい情報をご紹介します。
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの口コミや評判は、これから利用を検討する人にとってとても参考になる情報です。
利用者の声を調べると「担当者が丁寧に対応してくれた」「求人の質が良かった」という前向きな声がある一方で、「条件が合わず求人が少なかった」「連絡が遅いことがあった」という感想も見られます。
良い面と課題の両方を理解しておくことで、自分に合ったサービスかどうかを判断しやすくなります。
評判を事前に確認することは、不安を減らして納得感を持って登録するために役立ちます。
実際の口コミを読むと、自分と同じ境遇の人の体験談から学べることも多いです。
利用者の生の声を知ることが、安心した就職活動につながります。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
求人を紹介されなかったり、断られてしまうのは決して珍しいことではありません。
その理由は、希望条件が厳しすぎる場合やスキル・職歴が不足している場合、あるいは企業とのマッチングが合わなかった場合などさまざまです。
そのようなときは落ち込む必要はなく、自分の条件を柔軟に見直したり、スキルアップの準備をしてから再挑戦するのが効果的です。
資格取得や就労移行支援の利用などを通じて、少しずつ自分の強みを増やしていくことが重要です。
また、他のエージェントやハローワークを併用することで、選択肢を広げることも可能です。
一度断られても就職活動の道は閉ざされないので、前向きに次のステップを考えることが大切です。
関連ページ:dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
面談後に連絡がないと「忘れられているのでは」と不安になるかもしれませんが、必ずしも悪い意味ではありません。
繁忙期で対応が遅れていることや、面談内容から追加の確認が必要な場合、あるいは希望条件に合う求人が見つからず調整に時間がかかっているケースもあります。
通常は1〜3営業日以内に連絡があることが多いですが、それ以上待っても音沙汰がないときは、自分からメールで問い合わせをしてみると安心です。
遠慮せず「状況を確認したい」と伝えることで、その後の対応がスムーズになることもあります。
連絡が遅いからといってサポート対象外というわけではないため、落ち着いて行動することが大切です。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・求人・内定それぞれのケースと連絡なしの理由
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、これまでの職歴や体調の安定度、必要な配慮事項などを詳しく聞かれることが多いです。
面談は就職活動を有利に進めるための大切な機会であり、自分に合う求人を紹介してもらうためには、できるだけ正直に伝えることが重要です。
例えば「どんな働き方を希望しているのか」「どのような配慮があれば働きやすいのか」といった点を具体的に話すと、アドバイザーも求人を探しやすくなります。
事前に職務経歴書や配慮事項をまとめておくと、当日の面談がスムーズになります。
面談は緊張するかもしれませんが、自分の希望や状況を整理して話せば、より自分に合った提案を受けやすくなります。
関連ページ:dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がいのある方に特化した就職支援サービスで、求人紹介から面接対策、入社後のフォローまでトータルでサポートを受けられるのが大きな特徴です。
一般的な転職サイトと異なり、障がい者雇用枠に対応した求人を中心に扱っているため、自分に合った環境で働きたいと考える人に安心感があります。
担当キャリアアドバイザーが一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、必要な配慮や条件を踏まえて求人を提案してくれるため、ミスマッチを防ぎやすいのも魅力です。
さらに、登録や利用は無料であり、全国の求人に対応しているので幅広い選択肢から探すことができます。
就労に不安がある人でも、プロの支援を受けながら安心して活動を進められるサービスです。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジを利用する際、基本的には障がい者手帳を所持していることが前提となります。
障がい者雇用枠の求人は、企業が法的に雇用率を満たすために手帳を持つ人を対象にしているため、手帳がない状態では紹介できる求人が限られるのが現実です。
ただし、手帳を申請中の場合や、医師の診断書がある場合には相談に応じてもらえることもあります。
まずは主治医や自治体に手帳の取得について相談し、準備を進めておくと安心です。
どうしてもすぐに就職活動をしたい場合は、ハローワークや手帳不要の求人を扱うサービスを併用する方法もあります。
将来の選択肢を広げるためには、手帳取得を検討するのが有効です。
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジは、原則として全ての障害種別に対応しています。
身体障害、精神障害、発達障害、知的障害など幅広くサポート対象に含まれています。
ただし、症状が安定していない場合や長期的な勤務が難しいと判断される場合には、求人紹介が見送られることがあります。
これは「断られた」というよりも、まずは治療や就労移行支援などで準備を整えたほうが良いと判断されるケースです。
つまり、障害の種類そのものが理由で登録できないというよりも、就労が可能な状態かどうかが重視されます。
働きたい気持ちがあっても体調面に不安がある場合は、まずサポート機関を利用し、再度挑戦する流れが推奨されます。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジの退会は、公式サイトからマイページにログインし、登録情報の削除依頼を行うことで手続きができます。
また、担当アドバイザーに直接伝えても退会手続きを進めてもらえます。
退会理由は人それぞれですが、転職が決まった場合や、他のサービスを利用することにした場合などが多いです。
再登録も可能なため、今後またサポートが必要になった際に安心して戻ることができます。
退会は自由に行えるので、必要に応じて柔軟に利用できるサービスです。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
キャリアカウンセリングは、基本的にオンライン面談または電話で受けることができます。
全国対応しているため、地方在住でも安心して利用できます。
状況によっては対面での相談が行われることもありますが、多くの場合は自宅から参加できるので通院や体調への負担が少ないのが魅力です。
面談では職歴や体調、希望条件を丁寧にヒアリングされ、自分に合った求人や働き方を提案してもらえます。
事前に履歴書や配慮事項を整理しておくとスムーズです。
相談は何度でも可能なので、安心して利用できます。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには明確な年齢制限は設けられていません。
そのため、若年層から中高年層まで幅広い世代が登録可能です。
ただし、紹介される求人は20代から50代前半を中心とした内容が多いため、50代後半や60代以上では求人の数が限られてしまうことがあります。
これは企業が求める即戦力や勤務年数を考慮しているためです。
年齢が高い人でも、経験やスキルをしっかりアピールできれば採用の可能性は十分あります。
求人が少なくても、ハローワークや地域の支援機関を併用することで、選択肢を広げることができます。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
離職中の方もdodaチャレンジを利用することが可能です。
むしろ、在職中よりも時間に余裕があるため、面談や就職活動を進めやすいというメリットもあります。
離職してからのブランクが長くなると就職活動に不利になる場合もあるので、早めに登録して活動を開始することがおすすめです。
面談では離職の理由や体調の状況を丁寧に伝えることが大切で、そのうえで働ける環境に合った求人を紹介してもらえます。
離職中だから不利ということはなく、準備を整えながら進めることでスムーズに就職先を見つけることができます。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
学生でもdodaチャレンジに登録することは可能ですが、求人の多くは社会人経験者向けとなっています。
そのため、新卒枠やインターンシップの紹介は少なく、期待しているサポートを受けにくい場合もあります。
ただし、障がい者雇用枠に特化した就職活動の情報や、就労に向けたアドバイスを受けることはできます。
学生のうちに登録して準備を進めておくのも有効で、卒業後の就職活動に役立つケースもあります。
状況によってはハローワークや新卒向けの障がい者就職支援サービスを併用するのも良い方法です。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスと比較
dodaチャレンジを利用する際に気になるのが「断られることはあるのか」という点です。
結論から言うと、登録自体ができないケースは少ないものの、体調が安定していなかったり、希望条件が厳しすぎたりする場合には求人紹介を受けられないことがあります。
これはdodaチャレンジに限ったことではなく、他の障がい者就職サービスでも同じです。
例えばアットジーピーやサーナなどのエージェントでも、条件が合わないときは求人を紹介してもらえないことがあります。
一方で、地域密着型のハローワークや障がい者職業センターでは幅広いサポートが受けられるため、併用する人も多いです。
大切なのは「どのサービスを選べば自分に合う求人に出会えるのか」を見極めることです。
dodaチャレンジは全国規模の求人に強みがあり、他サービスと比較しながら利用することで、選択肢を広げやすくなるのが魅力です。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談まとめ
dodaチャレンジを利用した人の中には「求人を紹介してもらえなかった」「面談で断られてしまった」と感じるケースもあります。
理由として多いのは、希望条件が厳しすぎることや、職歴やスキルが不足している場合、あるいは体調が安定していないと判断された場合です。
また、地方在住や在宅勤務を強く希望している場合も、求人が少ないことから紹介が難しいとされることがあります。
しかし、断られたからといって就職活動が終わるわけではありません。
条件を見直したり、就労移行支援でスキルを高めることで、再度挑戦できるチャンスはあります。
実際に「一度は断られたが、スキルを磨いて再登録したら紹介を受けられた」という体験談もあります。
大切なのは断られた事実を前向きに受け止め、次にどう行動するかを考えることです。
体験談を参考にしながら、自分に合った準備を整えていくことが成功への近道です。