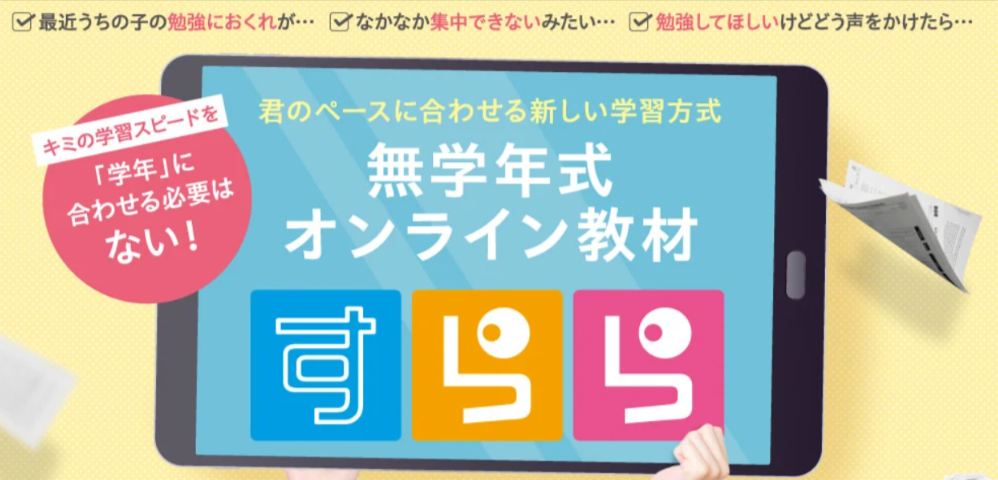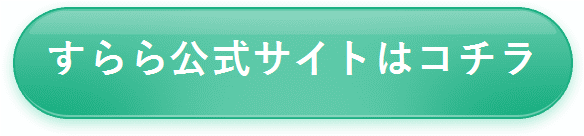すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
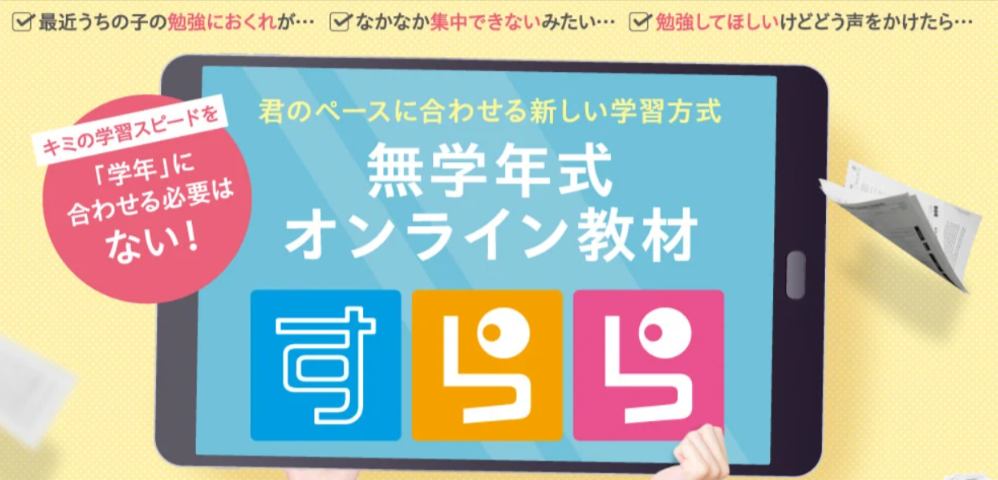
すららは自宅で取り組めるオンライン教材ですが、不登校の子どもにとっては「学校に行かなくても出席扱いになるの?」という点が気になるところです。
実際に、すららを使った学習は文部科学省が定める「ICTを活用した自宅学習」として認められており、条件を満たせば学校の出席日数に換算してもらえるケースがあります。
その理由は、学習の記録がシステム上に残り、学習証明レポートとして学校や教育委員会に提出できる仕組みが整っているからです。
さらに、すららコーチが作成する学習計画や進捗データをもとに「学校で学んでいる内容と同等」と判断されやすくなります。
これにより、不登校でも内申点に影響しにくく、進学時の不安も軽減されます。
もちろん、出席扱いにするかどうかは学校や自治体の判断によりますが、すららは全国で多くの実績があり、不登校支援の選択肢として注目を集めています。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららが不登校でも出席扱いとして認められやすい大きな理由のひとつが、学習の「質」と「記録」が明確に残ることです。
従来の家庭学習では「本当に勉強したのか?」を学校に証明するのが難しく、保護者の自己申告に頼るケースも多くありました。
しかし、すららではシステムが自動的に学習時間・進捗・理解度を記録し、レポートとして学校に提出することが可能です。
これにより、学校側も「客観的に学習している」と判断しやすくなり、出席扱いへとつながります。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、学習履歴が自動で蓄積され、どの教科を何時間取り組んだかが明確に分かるレポートが作成されます。
これを学校に提出すれば、出席扱いの判断材料として大いに役立ちます。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
家庭で保護者がいちいち学習記録をつける必要はありません。
自動的に見える化されるため、保護者の負担も軽く、学校にとっても「信用できるデータ」として評価されやすいのです。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
不登校の子どもは、学習のリズムが崩れやすく「続けられない」という悩みを抱えがちです。
すららでは、専任コーチが子どもの特性や理解度に合わせて学習計画を立て、定期的に進捗をチェックしてくれる仕組みがあります。
この「計画性」と「継続性」があることで、学校側からも「授業と同等の学習効果がある」と認められやすくなるのです。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
ただ学ぶだけでなく、きちんとした学習計画に基づいて継続して取り組めていることを証明できるのは、出席扱いの大きなポイントです。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
子ども一人に合わせた学習プランを作り、学習の進み具合を見ながら修正・調整してくれるため、学習の継続性が確保されます。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
「学年」に縛られず、必要なところから学べるため、不登校で学習に遅れがあっても取り戻しやすく、出席扱いにつながりやすい仕組みになっています。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
不登校の子どもが出席扱いとして認められるためには、「家庭」「学校」「教材提供側」の三者がスムーズに連携できることが重要です。
すららでは、この三者の橋渡し役としてサポートを行っており、家庭だけでは不安な手続きもスムーズに進めることができます。
担任や学校とのやりとりを保護者だけで背負うのではなく、すららのコーチがフォローしてくれるため、精神的な負担が軽くなる点も大きな魅力です。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
出席扱いの申請には学校や教育委員会に提出するための書類が必要です。
すららでは、必要なフォーマットや書き方のアドバイスをしてくれるため、保護者が迷うことなく準備できます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
学習時間や進捗をまとめた「学習レポート」は出席扱いの判断に重要な資料となります。
すららは専任コーチがフォーマットを用意し、提出までしっかりフォローしてくれます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
保護者だけで担任や校長とやり取りするのは大変ですが、すららが第三者的な立場で情報を整理し、連携をスムーズにしてくれるため、出席扱いに必要な調整が進めやすくなります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省が示す「ICTを活用した不登校児童生徒への学習支援」に対応した教材として広く利用されています。
単なる家庭用教材ではなく、公的に不登校支援の一環として認められている実績があるため、学校側も安心して「出席扱い」と認めやすいのです。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららはすでに全国の多くの学校や教育委員会で導入・活用されており、「出席扱いが認められたケース」が多数存在します。
この豊富な実績があることで、学校も前例を参考にしながら判断しやすくなるのです。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは文部科学省が定める基準を満たした「不登校支援教材」として公式に活用されています。
全国の学校や教育委員会との導入実績があるため、学校側も安心して「出席扱い」として認めやすい環境が整っています。
この公式な位置づけは、保護者や子どもにとっても安心材料となります。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
不登校でも出席扱いを認めてもらうには、家庭学習が学校の教育課程に準じていることが求められます。
すららはその条件を満たしているため、出席扱いとして認められる可能性が高いのです。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららの教材は文部科学省の学習指導要領に沿って作られているため、学校で学ぶ内容と一致しています。
これにより、家庭での学習も「学校と同等」として評価されやすくなります。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、単元ごとに理解度チェックや復習機能があり、学習の到達度を数値化して記録できます。
これらのフィードバックはレポートとして学校に提出可能で、学校側が「学習の成果」を客観的に確認できる仕組みになっています。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
すららは文部科学省が示す「ICT教材を活用した自宅学習」の要件を満たしているため、出席扱いとして認められるケースが増えています。
ただし、実際に出席扱いになるかどうかは、学校や教育委員会に申請して判断してもらう必要があります。
ここではその申請の流れを紹介します。
申請方法1・担任・学校に相談する
まずは学校に「すららを使った学習を出席扱いにできないか」を相談するのが第一歩です。
担任の先生や校長、またはスクールカウンセラーなどに話し、学校としての判断を仰ぐ必要があります。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
学校や教育委員会によっては、申請に必要な書類が異なる場合があります。
一般的には「学習記録」「教材の学習指導要領準拠の証明」「保護者の確認書」などが求められます。
事前に学校側に確認して、準備を整えましょう。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の理由が病気や発達障害、精神的な理由に基づいている場合、医師の診断書や意見書が求められるケースがあります。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
学校や教育委員会が「出席扱い」に判断する際に、客観的な証明として医師の診断書が重要視される場合があります。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書には「学校に行けない状態であること」と「自宅で学習を続けることが望ましい」旨を記載してもらうと効果的です。
これにより、学校側が出席扱いを認めやすくなります。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららは学習の進捗が自動で記録される仕組みになっており、保護者が手間をかけずにレポートをダウンロードできます。
これを学校へ提出することで、客観的な学習証拠として認めてもらうことが可能です。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららのマイページから学習進捗レポートをダウンロードし、担任や校長先生に渡すことで「家庭で継続的に学習している証拠」として提出できます。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
学校によっては専用の申請書があり、保護者が子どもの状況を記入して提出する流れになります。
すららのレポートとセットで提出すると承認されやすくなります。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
出席扱いは、最終的に学校や教育委員会の承認を経て決定します。
学校長や教育委員会が「学習状況が適切」と判断すれば、正式に出席扱いとして認められることになります。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
学校長が学習内容と記録を確認し、学習指導要領に沿っていると認めれば、出席扱いが決定します。
担任のサポートも大きな役割を果たします。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては教育委員会の承認も必要になるケースがあります。
その場合は学校と連携して書類を提出し、承認を得る流れになります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
すららは文部科学省の方針に沿ったICT教材として認められており、不登校でも出席扱いになるケースが増えています。
単に学習を続けられるだけでなく、出席扱いが認められることで得られるメリットは大きく、子どもや保護者にとって安心できる材料になります。
ここではその具体的なメリットについて紹介します。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
不登校になると出席日数が不足し、内申点の評価が下がることを心配する保護者は多いです。
しかし、すららを活用して出席扱いを認めてもらうことで、出席日数がカウントされ、評価が維持されやすくなります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
出席日数が確保できることで、欠席による内申点の低下を防げます。
特に高校受験や内部進学では大きな安心材料となります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席日数不足で進学に不利になる心配が少なくなり、子どもの将来の選択肢が広がります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校が長引くと「勉強についていけないのでは」と子ども自身が不安を抱きやすいですが、すららなら自分のペースで学び続けられます。
これにより、勉強の遅れを気にするストレスを軽減できます。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
毎日少しずつでも学習を進めていけば、学校の授業に戻ったときもスムーズに馴染めるようになります。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
「自分も勉強を続けられている」という実感は自己肯定感につながります。
学びの継続が自信を育てるポイントです。
メリット3・親の心の負担が減る
子どもが学校に行けない状況では、親も大きな不安を抱えがちです。
しかし、出席扱いが認められることで「学習や進学に悪影響はない」という安心感を得られます。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
担任や校長、そしてすららコーチと連携することで、保護者が一人で悩みを抱える必要がなくなります。
家庭と学校、教材が協力し合う環境が整うのは大きなメリットです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
すららは不登校の子どもでも出席扱いとして認められるケースが増えてきましたが、すべての学校で自動的に認められるわけではありません。
申請の際には学校や教育委員会とのやり取りが必要であり、注意点を理解しておくことでスムーズに進められます。
ここでは出席扱いを認めてもらうために知っておきたい大切なポイントを紹介します。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いを実現するためには、学校側の理解が何よりも重要です。
すららが文部科学省のガイドラインに基づいて設計された教材であることをしっかり伝え、信頼してもらうことが第一歩となります。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
学校が安心して承認できるように、教材の正当性を説明しましょう。
公式資料を活用すると説得力が高まります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
担任の先生に伝えるだけでなく、学校全体に共有してもらうことが大切です。
早めに校長や教頭に相談するとスムーズです。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
出席扱いを認めてもらうには、子どもの状況を客観的に示す必要があります。
特に精神的な理由や体調不良による不登校の場合、医師の診断書や意見書を添えることが求められることがあります。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
学校は医学的な裏付けを重視する傾向があるため、診断書は出席扱い申請において有効な資料になります。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書を依頼するときは、ただ「診断が欲しい」ではなく、出席扱いに必要であることを伝えるとスムーズです。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
医師に家庭学習の記録や子どもの様子を伝えると、診断書により具体的で前向きな内容を書いてもらいやすくなります。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いを認めてもらうためには、ただ自宅で勉強しているだけでは不十分です。
学校の授業と同等の学習内容や時間を確保する必要があります。
そのため、学習計画の立て方や実際の学習時間の確保が重要です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
学校側に認めてもらうには、教材やカリキュラムが「学校教育に準拠していること」が条件となります。
すららは学習指導要領に基づいているため、この条件を満たしやすいです。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
毎日長時間でなくても、学習時間を安定して確保することが求められます。
特に中学生以上では1日2〜3時間程度を意識すると安心です。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
国語・数学・英語だけではなく、理科や社会なども含めて学習していることが出席扱いの条件になる場合があります。
バランスを意識しましょう。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いは「学校と家庭の信頼関係」が前提となります。
家庭での学習状況を継続的に学校へ伝え、連携を取りながら進めることが重要です。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
学校が安心して承認できるように、学習状況を定期的に報告しましょう。
報告の有無で信頼度が大きく変わります。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららでは学習レポートを自動でダウンロードできるため、これを月1回程度学校に提出すると効果的です。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校が確認したいと考える場合、面談や家庭訪問の依頼があることもあります。
その際は協力的な姿勢を見せることで、承認につながりやすくなります。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
担任の先生に定期的に学習状況を伝えることで、学校側も安心して出席扱いを認めやすくなります。
メールや電話など、無理のない方法で進捗を共有すると信頼関係が築きやすいです。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
地域や学校によっては、学校長の判断だけでなく教育委員会の承認が必要になるケースもあります。
そのため、申請の流れをあらかじめ確認しておくとスムーズです。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会へ提出する資料は、学校と連携しながら整えていくのが基本です。
すららの学習記録や医師の意見書が必要になる場合もあるため、担任や校長と相談しながら準備すると安心です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
不登校のお子さんにとって「出席扱い」を認めてもらえるかどうかは、進路や内申点に大きく影響します。
すららは文部科学省ガイドラインに沿った教材であり、実際に多くの学校で出席扱いの前例があります。
ここでは、申請を成功させるための具体的なポイントを紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
出席扱いは最終的に学校長の判断によりますが、過去に他校で認められた事例を示すことで承認されやすくなります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
具体的な成功事例を提示することで、「自校でも認めても問題ない」という安心感を学校側に与えられます。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
実績のエビデンスを資料として持参することで、担任や校長に説明する際の説得力が格段に増します。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
学習の継続には本人の意欲が大切であり、学校側も「子ども自身が前向きに取り組んでいるか」を重視します。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
自分の言葉で取り組みを記録して提出することで、本人の学習意欲を客観的に示せます。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
保護者だけでなく本人が直接意欲を伝えることで、学校の先生方に「続けられる見込みがある」と信頼してもらいやすくなります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いの承認には「継続して学習できるかどうか」が大きなポイントです。
無理な計画では途中で挫折してしまう可能性があり、学校側からの信頼も得にくくなります。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
短時間でも毎日取り組めるようにすることが大切です。
「やりすぎない」計画のほうが長期的には成功につながります。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららの専任コーチは学習の進捗を把握しながら、子どもに合わせた無理のない計画を提案してくれるため、保護者の負担も軽減されます。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
出席扱いの申請では「学習状況を客観的に示す証拠」が必要になります。
そのサポートを強力に行ってくれるのが、すららコーチです。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
学習記録のまとめ方や学校への提出資料の準備など、コーチが具体的にアドバイスしてくれるため、スムーズに申請手続きを進められます。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
すららは、不登校の子どもが「出席扱い」として認められる事例が多く報告されています。
ここでは、実際に利用した保護者や子どもの口コミを紹介します。
不登校の不安や学習の遅れを感じていた家庭でも、すららをきっかけに前向きな変化が起きています。
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした…でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
中学2年から不登校になったお子さんを持つ家庭では、学習が止まることによる内申点への影響が一番の心配でした。
ですが、すららの学習記録を提出することで、学校から出席扱いを認めてもらえたという声があります。
おかげで内申点が大きく下がらず、進学への不安も和らいだそうです。
良い口コミ2・学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた!時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
不登校になると「勉強が進まない」焦りが強くなりがちですが、すららは1回10〜15分の短時間学習で進められるため、本人の負担になりません。
自由に時間を決めて学習できるので、プレッシャーが減り「やってみようかな」という気持ちになれたとのことです。
良い口コミ3・不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり…イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
保護者の口コミでは「家庭内の空気が改善した」という声が多いです。
何もせずに過ごしていた子どもが、すららを導入して少しずつでも学習を再開することで、親子関係のストレスも軽減したケースがあります。
良い口コミ4・小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
苦手科目が原因で不登校になる子も少なくありません。
すららはアニメーションを使った解説や繰り返し学習が可能なため、分からない部分を「置き去り」にせず丁寧に復習できます。
その結果、学習意欲が戻りやすくなるのが特長です。
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました、完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
半年ほど継続して学習を続けた結果、学校の授業に対する不安が減ったお子さんの事例です。
いきなり完全登校は難しくても、「部分登校」からチャレンジできるようになるケースもあり、不登校からの復帰のきっかけを作ってくれたという声が多いです。
悪い口コミ1・低学年だとすららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり、タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
小学校低学年では、タブレットの操作や学習の進め方がまだ難しい場合があります。
そのため、結局親が横について進めることになり、思っていたように「子どもが自分で学ぶ」スタイルにはなりにくいとの声があります。
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました、キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
すららのアニメキャラクターによる励ましは最初は楽しく感じても、続けていくうちに「飽きる」「うざい」と思う子どももいます。
特に「一人で学ぶことが苦手」なタイプの子には、学習意欲を保つのが課題になることがあります。
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした…教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
出席扱いは学校長や教育委員会の判断に委ねられているため、すららを導入しても必ずしも認めてもらえるわけではありません。
地域差や学校の理解度によって扱いが異なることがデメリットとして挙げられています。
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました、他のオンライン教材よりは高めの印象。
すららは無学年式で長く使える反面、月額料金は他のオンライン教材と比べるとやや高めです。
長期間利用すると経済的な負担を感じる家庭も少なくありません。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
すららは基礎からコツコツ積み上げる教材のため、すぐに成績が急上昇するわけではありません。
ブランクがある子どもの場合は、理解の定着に時間がかかることもあり、短期的な成果を求めると「効果が薄い」と感じやすいです。
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
近年、不登校という選択をする子どもたちが増えてきました。
さまざまな理由で学校に通えない状況の中でも、学びの機会を失わずにいられる環境はとても大切です。
そんな中で注目されているのが、タブレット学習サービス「すらら」です。
特に、すららは文部科学省のガイドラインにもとづいた活用方法を通して、在宅学習でも出席扱いにできる可能性がある教材として話題になっています。
でも実際のところ「本当に出席扱いになるの?」「申請の手続きはどうするの?」といった疑問や不安を持っている保護者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、すららの出席扱い制度に関するよくある質問にひとつひとつ丁寧にお答えしていきます。
不登校の悩みを少しでも軽くし、お子さまに合った学び方を見つけるためのヒントになれば嬉しいです。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららに関して「うざい」と感じる口コミがある理由は、人それぞれの学習スタイルや期待値とのギャップが原因になることが多いです。
たとえば、自分のペースで学習を進めたい子にとっては、すららのナビゲーションや繰り返しの指示が過干渉に感じられることがあります。
また、タブレット学習という特性上、声やキャラクターが苦手に感じられる子もいるかもしれません。
ですが、逆にそれが「丁寧で分かりやすい」と感じる子もいるため、決してすべての人に当てはまるわけではありません。
大切なのは、子どもにとっての“相性”です。
まずは無料体験などを通じて、実際の使い心地を確認してみるのがおすすめです。
【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには、発達障害のあるお子様向けに特化した料金プランが用意されています。
このプランは、通常の学習支援に加えて、発達特性に配慮したサポート体制が整っているのが特徴です。
たとえば、視覚支援や反復学習など、苦手に感じやすい分野への丁寧なアプローチが盛り込まれています。
さらに、療育手帳をお持ちの方や診断を受けている方には、料金が割引される場合もあるようです。
金額や申請手順については、すらら公式や提携機関の案内を参考にすると安心です。
月額費用やサポート内容が明確に分かるよう、事前にしっかり確認しておくことをおすすめします。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららのタブレット学習は条件を満たすことで「出席扱い」にすることが可能です。
これは文部科学省が定めたガイドラインに基づき、学校との連携を通じて申請されるものです。
具体的には、学校とすららの学習記録を共有し、子どもが一定の学習活動を継続していることを報告できれば、出席扱いとして認定されるケースがあります。
もちろん、校長先生の判断や学校ごとの対応にも左右される部分はありますが、すらら側でも申請のサポート体制が整っています。
不登校だからといって学びを止める必要はありません。
自宅学習でも、しっかりと学校生活の一部として認められる道が開かれているのは、とても心強いことです。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、期間限定でお得なキャンペーンコードが配布されることがあります。
これを利用することで、初回入会金が無料になったり、一定期間の月額料金が割引になるなどの特典を受けられます。
コードの入力は、公式サイトの申込フォーム内にある「キャンペーンコード入力欄」に記入するだけでOKです。
ただし、キャンペーンには有効期限がある場合が多いため、見つけた時には早めに利用するのが安心です。
キャンペーンの最新情報は、公式ページや提携先サイト、SNSなどで発信されることが多いので、こまめにチェックしておくとお得に始められますよ。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを退会する場合は、原則として「専用の退会フォーム」または「電話連絡」で手続きを進めます。
退会希望の月の前月末までに手続きを行う必要があり、月の途中で退会しても日割り返金はされませんので、タイミングには注意が必要です。
手続きの流れとしては、マイページやメールで連絡後、確認事項への返信を経て正式に完了する形になります。
また、再入会したい場合も新たに手続きが必要になりますので、念のため情報は控えておくと安心です。
退会理由について聞かれることもありますが、強引な引き留めなどはないため、気持ちよく解約できる仕組みになっています。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららの利用を検討する中で、入会金と毎月の受講料以外にどれくらいの費用がかかるのかは、保護者の方にとって気になるポイントですよね。
基本的には、すららの費用体系はとてもシンプルで、初回の入会金と月々の受講料以外に、強制的にかかる追加料金はありません。
ただし、お子さまにタブレットやパソコンが必要になる場合、それらの端末費用は別途かかります。
また、家庭でプリントを印刷する場合には、プリンターやインクなどの消耗品が必要になることもあります。
とはいえ、教材購入や塾のようなテキスト代は不要ですので、全体的には非常にコストパフォーマンスの良い学習サービスだと思います。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは、基本的に「1人1契約」が原則となっており、1つの契約で兄弟が一緒に使うことはできない仕組みになっています。
これは、それぞれのお子さまに合わせた学習履歴や進捗データ、苦手分析をもとに個別に学習プランが組まれるためです。
一見すると同じ内容を学ぶことができそうに見えますが、すららではコーチからのアドバイスや学習のフィードバックも個別に届きます。
そのため、兄弟で使いまわすような使い方では、サポートの質が落ちてしまう可能性があります。
ただし、兄弟で同時にすららを利用する場合には、入会金が割引になる兄弟割引が適用されることもあるようなので、そういった制度を上手に活用すれば負担は軽減できそうです。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには英語の学習コンテンツが含まれています。
小学校の英語教育が必修化されたこともあり、すららでは英語を基礎からしっかりと学べるようにカリキュラムが整えられています。
アルファベットや簡単な単語の読み書き、発音の練習はもちろん、リスニングにも対応しているので、英語に慣れ親しむにはとても良い環境です。
また、英語が苦手なお子さまにもわかりやすく学べるように、アニメーションや音声を交えて学習を進める設計になっているのも嬉しいポイントです。
自宅でリラックスした環境の中で、楽しく英語に触れることができるので、「英語が好きになった!」という声も多く聞かれます。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららでは、学習内容をただ提供するだけでなく、「コーチ」と呼ばれる専門スタッフからのサポートが受けられるのが大きな特徴です。
コーチは、学習の進捗を確認しながら、それぞれのお子さまに合ったアドバイスを届けてくれます。
たとえば、「この単元でつまずいているようです」や「今週は学習時間が少なめなので、次はここから始めてみましょう」など、具体的な声かけがあるのはとても心強いです。
また、学習計画の立て方がわからない場合にも相談ができるので、保護者の方の負担も軽くなります。
特に不登校のお子さまにとっては、画面越しでも「見守ってくれている存在」があるだけで安心感が生まれます。
親子で二人三脚ではなく、三人四脚で学びを進めていけるような感覚です。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
「不登校の子どもでも学びを止めたくない」「できれば出席扱いにしてあげたい」そんな思いから、家庭用のタブレット教材を探すご家庭は少なくありません。
でも、数ある教材の中で、どれを選べばいいのか迷ってしまうこともありますよね。
中でも「すらら」は、不登校の子どもに特化したサポートや出席扱い制度に対応している点で、他の教材とは少し違った魅力を持っています。
例えば、学習履歴の保存や学校との連携、発達特性に合わせた対応など、すららならではの工夫がたくさん詰まっているんです。
もちろん、チャレンジタッチやスマイルゼミといった有名な教材にもそれぞれの良さはあります。
この記事では、すららがなぜ不登校のお子さまにおすすめされるのかを、他の教材と比較しながらわかりやすくご紹介していきます。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。
|
16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
すららは、文部科学省の「出席扱いの要件」を満たすことにより、不登校のお子さまでも出席扱いとして認定される可能性があります。
これはすららが単なる家庭用学習教材ではなく、ICT(情報通信技術)を活用した正規の学習支援ツールとして機能しているからです。
出席扱いを申請するためには、まず保護者が学校に相談し、校長先生の判断のもと、学習計画書や学習の記録を提出する必要があります。
すらら側では、学習記録の提出や、出席扱い申請のためのガイドラインに沿った資料提供も行っているため、申請時のサポートが整っているのが安心できるポイントです。
ただし、学校ごとに対応方針が異なることがあるため、申請の前に事前にしっかりと話し合いの時間を持つことが大切です。
出席扱いは、制度を正しく理解し、丁寧に対応することで、実現できる可能性が広がります。